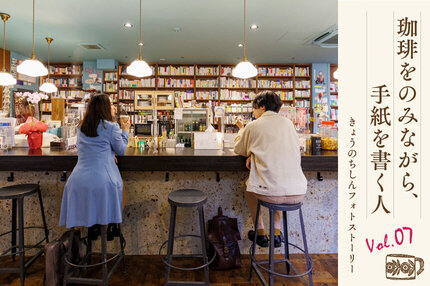この夏は、地蔵盆が中止になった町内も多いのではないでしょうか。
京都のまちには、さまざまなお地蔵さまが祀られています。
今回は、一目見ると忘れられなさそうな観音さまをご紹介します。
今出川通北白川、銀閣寺へ続く交差点。
そこに、高さ2メートルほどの大きな石仏が安置されています。
古くから子どもたちの成長や安全を見守ってきた「子安観世音(こやすかんぜおん)」。
「太閤の石仏(たいこうのせきぶつ)」ともよばれる観音さまで、鎌倉時代の作とされています。
自由に動き出すという噂が流れ、安土・桃山時代には太閤・豊臣秀吉のお気に入りに。
秀吉公は観音さまを自分の近くに置くため、聚楽第(じゅらくだい)へ連れて帰ります。
すると、北白川へ帰りたいと観音さまが夜ごとうめき声を上げたため、秀吉公は降参。
仕方なく元の場所に戻したという、なんとも不思議な逸話が残されています。
秀吉公が聚楽第に連れて帰る際に首を切ったことから、「首切観音」などの異名もあるとか。

子安観世音が祀られているのは、かつて「白川の村」とよばれていた地域の入口。
ここは当時、洛中から洛外の北へ向かう人々にとっての交通の要所だったといわれています。
子安観世音の脇には、小さなお地蔵さまがたくさん安置された祠(ほこら)も。
これらのお地蔵さまたちは、今出川通が整備された当時に地中から発掘されたものだそう。
子安観世音とともに、子どもたちや町内の安全を見守っています。

白川の村は、平安時代ごろより花の行商をしていた「白川女(しらかわめ)」で知られています。
摘みたての花が入った籠を頭にのせ、花を売り歩く姿は時代祭の行列でもおなじみですね。
今でも行商前には子安観世音に献花する習わしがあり、色とりどりの花が供えられています。
子安観世音(こやすかんぜおん)
京都市左京区北白川西町
京のお地蔵さま① 祇園・白川「なすあり地蔵菩薩」は こちら
時代風俗行列の最後を飾る「白川女献花列」 は こちら