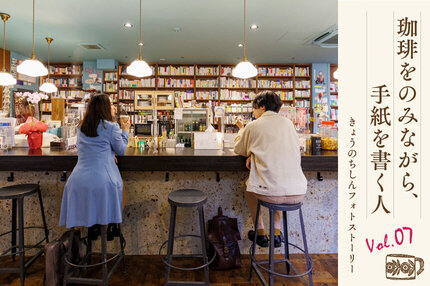八坂神社の祭礼である「祇園祭」の1ヶ月ですが、今年もひっそりとしています。
かつて、八坂神社の場所にあったというお寺に思いをはせてみませんか?
明治維新の神仏分離令まで、現在の八坂神社の場所に「祇園社 感神院」というお寺があったとか。
京都の「祇園」という地名は、この祇園社に由来しているといわれています。
今回は、江戸時代に祇園社と深いゆかりのあったお寺をご紹介します。
東山二条の「引接山 極楽院 大蓮寺」で、「安産祈願の寺」としても知られています。
明治時代の神仏分離令による廃仏毀釈(はいぶつきしゃく)によって、祇園社が廃寺に。
その際、祇園社の観慶寺にあった仏像や仏具がすべて大蓮寺に移されたといわれています。
祇園社の本尊だった重要文化財「薬師如来」などは秘仏で、拝観することはできません。
洛陽三十三所観音霊場の第8番札所であるため、「十一面観音菩薩」は1年を通して拝観が可能です。
 大蓮寺の御本尊・阿弥陀如来は「あんさん(安産)」とよばれ、安産祈願にご利益があるとか。
大蓮寺の御本尊・阿弥陀如来は「あんさん(安産)」とよばれ、安産祈願にご利益があるとか。
江戸時代、後光明天皇が、典侍・庭田秀子の安産祈願を大蓮寺に命じました。
無事に第1皇女・孝子内親皇が誕生したことから、後光明天皇の勅願所になったといわれています。
また、明治から大正時代にかけては、洛中洛外を駆けめぐった「走り坊さん」の寺としても話題に。
当時、歩いて参拝できない妊婦さんのために、走って御守を届けたという「走り坊さん」。
晴れの日も雨の日も、大蓮寺と阿弥陀如来の使いとして走り回ったという伝説が残されています。
現在は納経所で「走り坊さん」の「足腰健常の御守」が授与されています。
駅伝の発祥の地・京都で、市民ランナーやアスリートからの信仰も厚いそう。
「走り坊さん」のように、足腰に不安を感じている家族や友人のもとへ届けるのもよいですね。

大蓮寺の開基は慶長5年(1600)、五条若宮(現在の五条西洞院あたり)と伝わります。
昭和20年(1945)、戦時中の強制疎開により、現在地の東山二条に移転しました。
その名のとおり「蓮の寺」としても知られ、開花シーズンは6月下旬から8月中旬ごろまで。
境内には40数種類の花ハスの鉢があり、早咲きから遅咲きまで色とりどりの花を楽しめます。
例年、梅雨の晴れ間に開花がすすみ、梅雨明けに最盛期を迎えるという花ハス。
平年の京都の梅雨明けは、祇園祭(前祭)の山鉾巡行を過ぎたころ。
今年の梅雨明けはいつになるのでしょうか。
太陽の下で見事に咲くハスの花を思えば、これからの暑さも乗り越えられるかもしれません。
開花状況は、大蓮寺の公式ウェブサイトやYouTubeチャンネルにアップされています。
お出かけが難しい人は、おうちにいながらハスの開花を楽しんでみてはいかがでしょうか?
引接山 極楽院 大蓮寺(いんじょうじ ごくらくいん だいれんじ)
京都市左京区東山二条西入1筋目下ル457
市バス停東山二条または東山仁王門下車、徒歩5分
祇園祭に思いをはせる「疫病退散祈願 コラボ御朱印」 はこちら