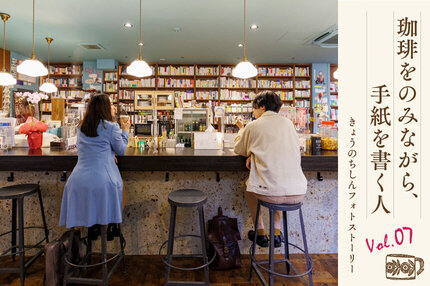1月5日は「囲碁の日」。
そして、1月15日は「いい碁の日」に制定されています。
寺町通夷川にある、囲碁「本因坊」発祥の地。
発祥の地を伝える駒札の下には、石でできた碁盤も設置されています。
囲碁のタイトルのひとつとして知られる「本因坊(ほんいんぼう)」。
安土桃山時代、この地には「寂光寺」というお寺が建っていました。
その塔頭である本因坊に住んでいた寂光寺2世・日海上人(にっかいじょうにん)は、囲碁の名手。
その腕前は、織田信長、豊臣秀吉から徳川家康らがこぞって師事するほどだったとか。
信長からは「名人」の号が、秀吉からは「碁」の役職が与えられたといわれています。
さらに江戸時代には家康が日海上人を江戸へ呼び寄せ、幕府の「碁所(ごどころ)」に任命。
日海上人は名を本因坊算砂(ほんいんぼうさんさ)に改め、碁道本因坊の開祖となりました。
のちに家元制は廃止、寂光寺塔頭の本坊因も消滅してしまいました。
本因坊の名跡を継承する囲碁の棋戦「本因坊戦」が、本因坊の名を今に伝えています。

平成21年(2009)に駒札と碁盤が設置された際、今村九段と滝口九段による打ち初め式を執行。
現在もこの碁盤に碁を持ち込めば、誰でも実際に碁を打つことができるようですよ。
碁盤といえば、洛中のまちなみを表現する「碁盤の目」。
碁盤の目のなかにある碁盤で対局できるなんて、京都ならではの光景かもしれません。

さて、「囲碁本因坊の寺」とよばれる寂光寺。
2度の移転を経て、宝永5年(1708)に現在地の東山仁王門で再興されました。
歴代本因坊の墓所があり、本因坊算砂が愛用した碁盤や碁石が寺宝として所蔵されています。
囲碁「本因坊」発祥の地(いご ほんいんぼう はっしょうのち)
京都市中京区寺町通夷川上ル
地下鉄京都市役所前駅から徒歩5分
寂光寺(じゃっこうじ)
京都市左京区仁王門通東大路西入ル
市バス停東山仁王門下車、徒歩2分