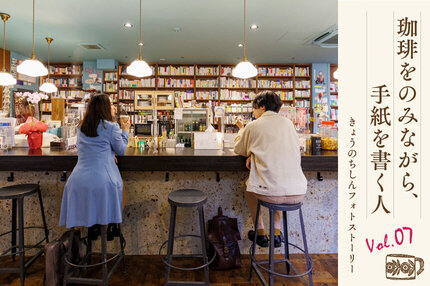1000年の歴史の中で幾度となく厄病が流行し、各地で厄病を鎮める神事などが行われてきた京都。
神事の際には、疫病除けのご利益があるとして菓子や餅などが奉納されてきました。
今回は厄病除けの霊社として名高い、御靈神社(上御霊神社)の門前菓子をご紹介します。
今から540年以上前、文明9年(1477)に創業したという「水田玉雲堂」です。
こちらの名菓「唐板(からいた)」の始まりは、さらに今から1160年近くも前。
貞観5年(863)に京都で大流行した厄病がきっかけだったとか。
当時、悪疫退散のために神泉苑で「御霊会(ごりょうえ)」が行われていました。
その際に奉納された唐板煎餅が、「唐板」の原型だといわれています。
唐板煎餅は、御靈神社の祭神のひとり、吉備真備が奈良時代に遣唐使として中国に渡って持ち帰ったもの。
しかし、御霊会は室町時代の応仁の乱(1467~1477)で廃絶してしまいます。
乱後、水田玉雲堂のご先祖が過去の記録をもとに唐板煎餅の作り方を会得、再興に至ったとか。
御靈神社の境内で茶店を開き、「唐板」は厄除け菓子として愛されるようになったそうです。

昭和初期に、現在地である御靈神社の鳥居前に移転した「水田玉雲堂」。
創業以来540年以上もの間、「唐板」1種類のみを製造販売し続けています。
「唐板」の材料は小麦粉、砂糖、鶏卵と、いたってシンプル。
その反面、想像以上に複雑な工程で作られているのも奥深さの所以のひとつです。
1枚ずつ丁寧に手焼きで作られた「唐板」は、驚くほどサクサクほどける食感。
薄い短冊形に切り分けられ、どことなく厄除けのお札にも見えるような気がします。
御靈神社の参拝帰りに、ぜひ買い求めてみてはいかがでしょうか?
水田玉雲堂(みずたぎょくうんどう)
京都市上京区上御霊前通烏丸東入ル上御霊前町394
地下鉄鞍馬口駅から徒歩3分