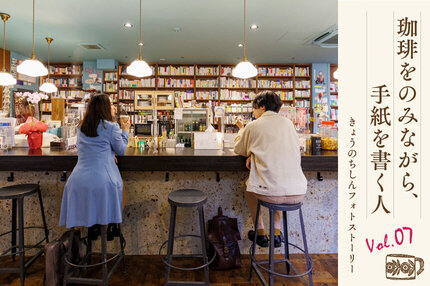京都のまちを歩いていると、町家の小屋根などから気配を感じることがあります。
その正体は「鍾馗(しょうき)さん」。
中国の民間伝承として広まった、疫病よけなどにご利益のある道教系の神さまといわれています。
京都では民間信仰のひとつとして、町家の小屋根などに鍾馗さんの焼き物が置かれるのが一般的。
向かいの屋根の鬼瓦などから弾かれた邪気を払ってくれる、町家の小さな守り神とされています。
そんな鍾馗さんを正式に神格化して崇めている「鍾馗神社」をご存じでしょうか。
陶祖神・椎根津彦命(しいねつひこのみこと)をまつる「陶器神社(若宮八幡宮社)」の末社。
鍾馗さんも瓦から作られた焼き物であることにちなみ、平成25年(2013)に建立されました。
境内の駒札によると、鍾馗神社を建立したのは、京都造形芸術大学(現・京都芸術大学)の教授。
鍾馗さんの御神体は、同大学で当時、美術工芸学科だった学生さんによる制作だそうです。
屋根の上の鍾馗さんの何十倍もありそうな特大サイズの御神体は迫力満点!
参拝者とにらみ合うことがないよう、視線がしっかりそらされています。
よく見ると、大きな鍾馗さんの足もとには小屋根の上にいるのと同じくらいの小さな鍾馗さんが。
さらに、対になった鍾馗さんも阿吽(あうん)像のように参拝者を出迎えてくれます。
京都のまちで存在感を放つ鍾馗さんですが、鍾馗さんをまつる神社は日本でここだけだとか。

鍾馗神社があるのは、清水焼発祥の地として知られ、古くからの京町家が多く残る五条坂。
鍾馗神社の2軒西隣りにある、老舗陶器店「陶点睛 かわさき」の鍾馗さんに注目を!
なんと、陶器店ならではの白い陶器の急須を持った、独特のスタイルの鍾馗さんなのです。

今は京都のまちも人が少なくなって、鍾馗さんもさみしがっているかもしれませんね。
世の中が落ち着いたら、まち歩きを楽しみながら鍾馗さんを探してみてください。
そのときはぜひ、鍾馗神社へもお参りしてみてはいかがでしょうか。
鍾馗神社(しょうきじんじゃ)
京都市東山区五条橋東五丁目480(陶器神社内)
市バス停五条坂下車、西へ徒歩5分