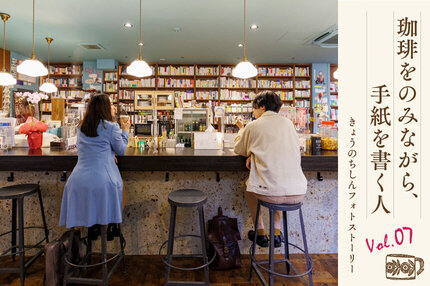8月1日は「八月朔日(さくじつ)」、縮めて「八朔(はっさく)」とよばれています。
「月の最初の日」を意味する「朔日」。
京都の八朔といえば、新暦の8月1日に花街で行われる挨拶まわりの風習ですね。
例年、八朔には芸妓さんや舞妓さんが正装でお茶屋さんや芸事のお師匠さんのもとへ。
「おめでとうさんどす」「おたの申します」などと、日ごろの感謝を伝える伝統行事です。
京都のお中元の起源となった日でもあり、各家庭でもこの日よりお中元の挨拶が始まります。
また、旧暦の八朔は9月の中ごろで、ちょうど早稲(わせ)の穂が実り出す時期。
2020年は、9月17日が旧暦の八朔にあたります。
農業を営む人々の間では、お世話になった人々に初穂を贈る風習があったとか。
初穂の収穫に感謝し、田の神様に豊作を願ったことから「田の実の節句」などの呼び名も。
「田の実」が転じて「頼み」となり、現在のお中元につながっているといわれています。
ところで、「はっさく」と聞くと、口の中が酸っぱく、みずみずしくなる気がしませんか?
実はあの果物のハッサクは、江戸時代に広島県の浄土寺で偶然、発見されたものだそう。
ご住職が「八朔のころには食べられる」と言ったことが、名前の由来だといわれています。
もちろん、現在では八朔のころにハッサクは出回らず、主に2~4月に食べごろを迎えます。
伝統行事などが相次いで中止、規模縮小される今年も、心豊かで実りある日々となりますように。
※2020年はコロナウイルス感染防止のため、五花街での「八朔」行事は行われないようです。