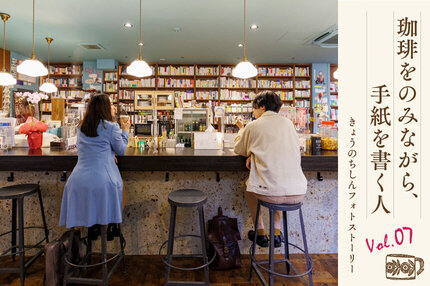京都三大祭のなかで、新緑がまぶしい初夏に行われる葵祭。
今年は新型コロナウイルスの影響で、5月15日の「路頭の儀」は中止です。
京都には、祭などのハレの日に鯖(さば)寿司をいただく風習が根づいています。
葵祭や祇園祭、時代祭の食卓にも欠かせない、江戸時代に生まれたといわれる町衆の食文化。
代々受け継がれる家庭の味はもちろん、鯖寿司の専門店もたくさんあります。
江戸時代、若狭(福井)の海で水揚げされた海産物を、京都まで担ぎ手が運んでいました。
その距離は、最短にして18里(約72km)といわれています。
若狭では特にサバが多く獲れ、足の早いサバを塩でシメて鮮度を保つ知恵と工夫が生まれました。
京都へ到着するころにはすっかり塩サバとなり、海から遠い京都でとても珍重されたとか。
海産物を運んだ道は鯖街道とよばれ、なかでも福井の小浜と京都の出町を結ぶ若狭街道が有名に。

出町橋西詰には「鯖街道口」の石碑が立ち、歴史と食文化を今に伝えています。
その鯖街道口からほど近い場所にある「鯖街道 花折 下鴨店」。
大正2年(1913)創業の京鯖ずし店で、現在はネットショップでも鯖寿司をお取り寄せできます。
今年は葵祭の路頭の儀を見学することは叶いませんが、鯖寿司を並べて祭に思いを馳せませんか?
詳細は「鯖街道 花折」の公式ウェブサイト(ネットショップ)で確認してください。
鯖街道 花折 下鴨店(さばかいどう はなおれ しもがもてん)
https://www.hanaore.co.jp/smp/