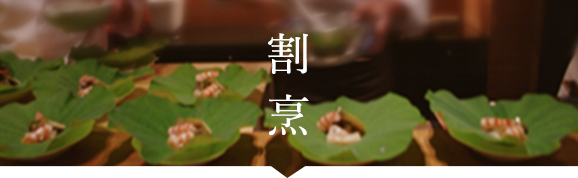料亭「木乃婦」の三代目主人が考える精進料理とは?その進化や精進料理への思いについて語っていただく連載【精進料理知新】今回は、海外に精進料理をどう発信していくかについてお話いただきました。
料亭「木乃婦」の三代目主人、高橋拓児さんは、2015年より京都料理芽生会創立60周年事業で同会が取り組んだ「精進料理の世界へ」をメンバーともに推進してきました。現在も自身の店で、お客さんの要望に応えるかたちで精進料理に取り組んでいます。高橋さん自身が考える精進料理とは?その進化や精進料理への思いはいかに?というテーマで5回にわたって、語っていただきます。
※「京都料理芽生会」/日本料理の発展と、伝統と格式のある京都の食文化を次世代へ継承するために1955年に設立。京の料亭の若主人たちが研鑽・研究を行い、様々な挑戦を行っている。
SHOUJINから回心へ
私の店でも、精進料理のコースの予約は年々、増えています。厳密な意味での精進料理というよりは、ヴィーガンの方や、ハラル食を希望される方などに精進料理の考え方で対応すると、問題なく、食事を楽しんでいただけるんです。
1日1組は最低、そういったご要望があるものですから、厨房では、前回お話しした独自で引いた濃厚な昆布だしや、卵を抜いた玉味噌のストックは欠かせません。
ただ、今、お話していることは、食材、つまり"かたち"のことだけなんですね。そこに精進料理の精神性までは伝えられていないと思うんです。
野菜だけを使う、肉や魚を使わない。そういう捉え方で、「なんとなくSHOUJIN」という感じは、海外のお客様に伝わっているとは思うのですが...。でもそれは、SUSHIやTEMPURAとして伝わっている日本料理の段階とそう変わりはないのとちがうかなと感じています。
私自身、ここ何年か、精進料理に取り組んできて、やはり、その背景にある禅、仏教のことについて自分自身がよくわかっていないことを痛感していて、少しずつですが、禅や仏教のことを知ろうとしているんです。
仏教に「回心」という言葉がありますが、これは「知」と「情」を掛け合わせたものといわれています。
「知」は主観的なもの。形式を知ってはいるけれど、知っているだけというあくまで主観的なものを指します。
「情」は客観性があるもので、人間の叡智によって論理的にストーリーを描けること指します。
この「回心」の「知」と「情」を料理に生かすことが、精進料理に関わる際に非常に大切なことではないかと、私は考えています。「美味しい」と感じることの、その背景に潜むもの。どういう素材で誰がどう考えて料理したのか。それをどうやって伝えていくのか。ここに「回心」が深く関わっていくはずです。
「置き換える」ことの大切さに気づく
「なんとなくSHOUJIN」は、まず、そこかスタートすればいいと思うんです。でも、そのレベルを少しずつ上げていって、最後どこを目指すのか?というと、これはもう典座の境地に至るということなんですね。
作る方だけでなく、食べる人自身が、精進料理を「典座」の気持ちで理解できるようになって、「知」と「情」が掛け合わされるんです。
たとえば、海外の人が、自分の国で真剣に、本格的に湯葉をつくりはじめるような(笑)感じでしょうか。まあ、そういうことが一つでも起こって、はじめて、「SHOUJIN」が「精進料理」として海外に伝わったといえるのではないでしょうか。
では、店で料理をお出しする立場としてはどうか。
一度、召し上がっていただけでは、もちろん、そこまで到達できませんから、リピートしてくれたお客様には、2回目には少し、典座のことをお話ししてみる、3回目になったら禅寺を紹介して座禅を体験してもらい、その上で、精進料理を召し上がっていただく。そんなことをおそらく何十年もかけないと、「伝える」ことは無理でしょうね。もしかしすると我々の次世代でようやく実現するかもしれません。でもね、今、確かに精進料理は、海を超えていきつつありますよ。それは日々、実感しています。
どんな人も共に食事を。ピースフルな食、精進料理
こちらが「伝えようとすること」をやめなければ、相手も、何かきっと、ほんの少しの「気づき」や「腑に落ちる」といった体験ができると思うんです。霊的な体験というと驚かれるかもしれませんが、私自身、精進料理に取り組むうちに、ふと「あ、そうだったんや!」という、天啓のような気づきが何度かありました。
困った時にいつもするのが「典座の仕事を自分の仕事に置き換えてみる」ということ。これは日々のくせみたいなものになってしまいました(笑)。
でも、この、いったん「置き換える」という段階を入れることで、八方ふさがりと思っていたのにすっと抜け出せたり、思わぬヒントに出会えたり...。ほんの少しだけ、典座の境地に近づいているのかな。でもそんなことを考えているうちは、あかんのですけどね(笑)
大使館のレセプションで料理をさせていただく時など、いろいろな国の人、いろいろな宗教の人が同じ食卓につくということがあるんですね。以前でしたら、あれもダメ、これもだめ、あちらを立てれば、こちらが立たずで、頭を抱えていたと思うんです(笑)。
でも、精進料理の考え方で取り組むと、これがとてもうまくいくんですね。
ムスリムの方もヒンドゥーの方も、ヴィーガンの方も、どんな人がいても共に食事ができる。これって、じつにピースフルですよね。これはほんまに素晴らしいことやと思います。
混沌としたこの時代、グローバリゼーションも行き着くところまでいった感がありますが、精進料理はもしかするとその突破口になるかもしれません。
次回は最終回となりますが、精進料理の可能性についてお話ししたいと思います。
取材・文 郡 麻江

■ 木乃婦
京都市下京区新町通り仏光寺下ル岩戸山町416
075-352-0001
12:00~14:30(L.O.13:00)、18:00~21:30(L.O.19:00)
定休日 水曜