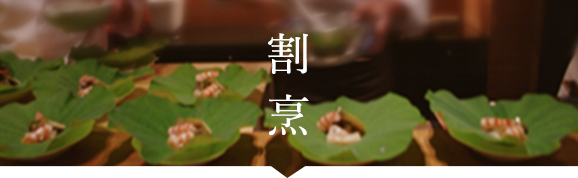料亭「木乃婦」の三代目主人が考える精進料理とは?その進化や精進料理への思いについて語っていただく連載【精進料理知新】今回は、精進料理への思いについてお話いただきました。
料亭「木乃婦」の三代目主人、高橋拓児さんは、2015年より京都料理芽生会創立60周年事業で同会が取り組んだ「精進料理の世界へ」をメンバーともに推進してきました。現在も自身の店で、お客さんの要望に応えるかたちで精進料理に取り組んでいます。高橋さん自身が考える精進料理とは?その進化や精進料理への思いはいかに?というテーマで5回にわたって、語っていただきます。
※「京都料理芽生会」/日本料理の発展と、伝統と格式のある京都の食文化を次世代へ継承するために1955年に設立。京の料亭の若主人たちが研鑽・研究を行い、様々な挑戦を行っている。
そもそも精進料理とは?
まず、精進料理とはどんな料理なのか、基本的な決まりごとからお話しましょう。「精進」とは悟りを得るための仏道の修行のことを指します。その修行の中に食事も含まれるます。食事と作ることも、また、食べることも修行となるわけです。
作る際の決まりごとは非常に厳格で、不殺生戒の教えによって肉類、魚介類は一切使いません。また「葷」と呼ばれるニラ、にんにく、ねぎなど匂いの強い食材も避けるよういします。基本的に、野菜、豆、穀物を使って料理を作ります。この教えは鎌倉時代に曹洞宗の開祖である道元禅師が、南宋に留学した時に「食も大切な修行である」ことを悟り、料理をする者の規範となる「典座教訓」(てんぞきょうくん)と食べる側の心得を説いた「赴粥飯法」(ふしゃくはんぽう)を著したことがもとになっています。
典座というのは寺の中で料理を担当する僧のことで。典座は食材の命の尊さを常に念頭におき、無駄を出さず、根や皮なども使い切るようにします。「五法」と「六味」を基本に、ひたすら料理に打ち込みます。
「五法」と「六味」については、次回、お話したいと思いますが、振り返れば、私が4〜5年前に精進料理に取り組み始め時、今、お話したような精進料理の概要というか、アウトラインだけを意識して、料理をしていたんやなあとつくづく思います。要するに、自分自身の心構えとか考え方が浅はかやったなあと...(笑)。"魚を使わなければいいんだな"とか、"匂いの強いものは避ければいいんだな"とか、要するに心は置き去りで、どちらかというとルールに則ってその料理をおいしくすることにのみに集中して、そこに何の疑念も抱かずに料理を作り始めていたんですね。自分の精神の部分が全くついていっていなかったと思います。
習気(じっけ)によって体得する、典座の心構え
「京都料理芽生会」の精進料理がきっかけになったと思いますが、4年ほど前からうちの店にもお寺さんとか精進料理に興味を持つ方、そしてベジタリアンの方などから、精進料理のご要望が増えてきました。それで自分なりに一生懸命考えて、自分なりの精進料理をお出しするようになりました。
お寺さんの大切な行事の時にもお料理をさせていただくんですが、「こんなん精進料理とちがうよ」とお叱りを受けたり、反対に「この食材の組み合わせは面白いなあ」とお褒めを受けたり、自分もなんで叱られたんか、なんで褒められたんか、わからないんですよ(笑)。その度に考えて、悩んで、また料理を作るというのを繰り返してきました。
そうする中で、だんだんと、本当に少しずつですが、精進料理の根本というのは、食材や調理法のルールを守ればいいというものでは全くなく、作り手がまさに典座と同じ心持ち、心構えで取り組まなあかんのやということが、おぼろげにわかってきました。
「習気」=じっけという言葉が禅の言葉があるんですけど、わかりやすくいうと、"気づき"だと思うんです。習いながら、日々、実践しながら学んで、そうして気持ちがだんだんと入っていく。その繰り返しの中で、わかってくるもの、気づくものがあるんだろうなと...。
でも、やっぱり料理屋ですからね、美味しくしたいとか、美しく見せたいとかいう気持ちが働くんです。それは料理のプロとして当たり前なんですが、それって精進の世界からしたら「俗」なことであり、浄らかでなくなってしまうんです。
料理のプロとしての自我をぐっと抑える修養の場
料理にも色味ってありますでしょう?精進料理の場合は、まず基本が土の色なんです。黒、茶色、白がまずあって、そこにほんの少しの常若の緑と、浄土の蓮を表す赤とを、上手に組み合わせて、派手すぎず、色を抑えてバランスよく仕立てていくんです。要はお浄土の世界を料理で表現するわけですね。
色を抑えるのには理由があって、お寺の本堂で一番中心となるのは、みほとけです。金色に輝く仏さまが中心で、周りのものはそれを引き立てるための色彩であるべきなんです。精進料理もそれは同じです。
お弁当一つとっても花見弁当とか、紅葉弁当とかあるけど、精進の場合はぐっと抑えた感じにせなあかんわけです。
ここにこの色味を加えたら、雅びで綺麗になるなあと思った瞬間、その思いをね、ぐっとこう地を這うように抑えるわけです。心を制御しなあかんのです。私らにしたら、もうその心を抑えること自体が修行みたいなものになるわけです。
綺麗に見せたいという気持ち自体が自我であり、自我を抑えて料理をするというのは、最初は苦しいものがあったんですが、だんだんと、先ほどの習気(じっけ)というか、腑に落ちることが増えてきました。それが何なのか?というのを、具体的にこれ!と指し示すのは難しいですが、一つ言えるとすれば、素材をじっと見つめて、その背景に思いを寄せて、それ素材の本質を明らかにしていく姿勢が自分の中にできてきたように感じます。外に向かって明らかにするのではなく、むしろ自分の心の中で明らかにして、得心してから料理に臨む、そんな感覚が深まっていくように思います。
気持ちから入っていく。それが第一歩
精進料理は、作り手の成長と料理の完成度というのが、比例して良くなっていくものなんだと思います。
いつ、どこで、どなたのためにどんな料理をお出しするのか、どういう目的で、どういう環境でいただく料理なのか。そういうことを、素材を目の前にした瞬間から、ずーっと考えて、考えて、深めていくんです。しかもそこに正解というものはない。ほんまに気の遠くなるような世界です。
精進料理を極めるには、一夕一朝では絶対に無理だし、まさに習気の領域で一つずつの積み重ねの中から培っていくしかない。知識も技術も工夫も必要ですが、技を磨いたり、決まりごとを守るとかの前に、まず気持ちをきちんと入れていくこと、そこが肝要だと思います。
「典座教訓」が示すように、料理すること自体が修行ということを日々、体感するほかに道はないんでしょう。
私も、その道の端っこがほんの少しだけ見えてきたところに立っているだけで、何かがわかった訳では全くないんですけど(笑)。
でも、追い込まれた状況で必死に考えるうちに、常に深く考える癖だけはついてきたようには思います。昨日考えたことよりも、今日考えたことの方がより深まっていく。それでこそ、今日一日を生きた意味があるんじゃないでしょうか。
今回のお話は、精進料理を料理する側の気持ちのありように終始しましたが、まずそこがスタートやと思っています。第二回では、そのあたりをもう少し具体的な内容で、実際の調理法などを交えて、お話したいと思います。

■ 木乃婦
京都市下京区新町通り仏光寺下ル岩戸山町416
075-352-0001
12:00~14:30(L.O.13:00)、18:00~21:30(L.O.19:00)
定休日 水曜