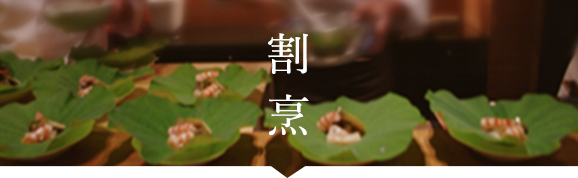これを知っておけば大丈夫!料亭・割烹の楽しみ方やマナーをわかりやすく解説します。
緑滴る東山麓の懐に抱かれるように建つ、料亭「菊乃井」。大正元年、創業以来、京都を代表する名料亭として、多くの人々に愛されてきたこの店の三代当主、村田吉弘さんは、「和食とは何か?」を常に問い続け、それを使命に様々な活動を続けている。現在はNPO法人日本料理アカデミー理事長に就任し、「日本料理を正しく世界に発信すること」を自らのライフワークとして掲げ、「和食」つまり、日本の伝統的な食文化のユネスコ無形文化遺産への登録に尽力した。その村田さんに「和食とは何か?」について語っていただくシリーズの今回は第四回、「世界に拓く日本料理」をテーマにお話をいただいた。
料理にも味にも、国境なき時代の到来。
今、世界はものすごく近くなっていますよね。たとえてみれば、玉転がしの玉ぐらいの大きさやったものが、今はゴルフボールぐらい小さくなっていると思うんです。
情報も流通も発達して、料理にも味にも国境というものがなくなりつつあると感じています。
僕がずっと長く関わっている活動に、「日本料理アカデミー」があります。このアカデミーでは、日本食文化の継承を目指しつつ、日本人自身に日本の食文化を見直してもらい、さらには和食への正しい理解を世界の人に広めていきたいと、世界中のシェフとの交流をはじめ、いろいろな活動を展開しています。
たとえば、世界に日本料理を正しく発信するための「日本料理大全」の編集と出版もその一つ。このシリーズは、世界のシェフに読んでもらうために日本語版、英語版、イタリア語版があり、現在、第4巻まで手がけています。
今、世界の中にあって和食は大変、注目されています。まずヘルシーであること、
季節感を豊かに取り入れ、器や盛り付けなど見た目の美しさと、味わい、美味しさが見事に融合していることなど、理由はたくさん挙げられますが、アカデミーが積み上げてきた地道な活動がその下支えになっていると自負しています。
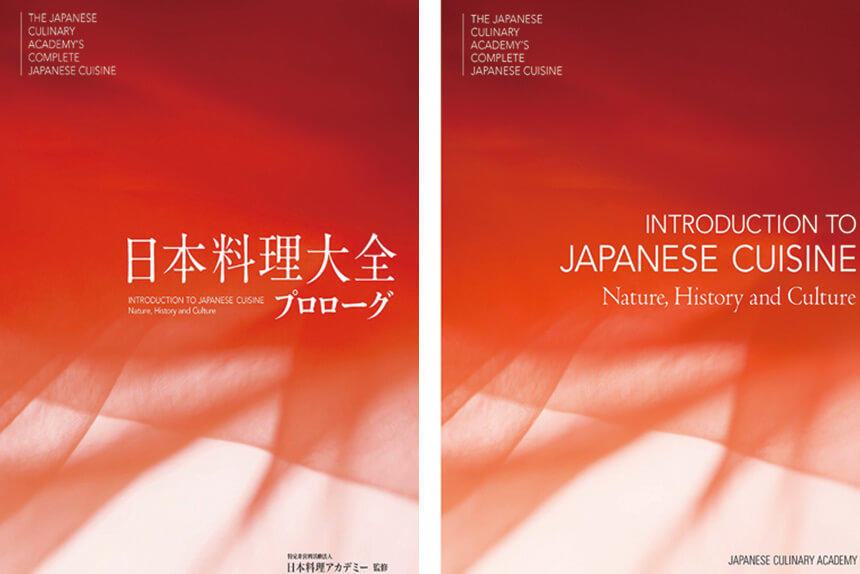
世界に広がる日本料理。今、我々は何ができるのか。
和食が2013年に世界遺産に登録されてから、世界中の日本料理店はどんどん増え続けて、登録前に5万6000軒だったのが、今、日本以外で12万3000軒にものぼっています。ところが指導者も不足していますし、「こんなん和食ちがうわ」という店もたくさんあるようなんですね(笑)。
「そういう店は続けてもらったらあかんのとちがうか?」という、もっともな意見もありますが、僕はまず、和食に興味を持って作ろうとしてくれる、その人たちの姿勢がありがたいし、そういう人たちはとても貴重な存在やと思うんです。
そやから、今は、たとえば盆栽を育てるように細かい剪定を最初からあれこれ入れるより、まずは大木に育って欲しいと思っています。それぞれの土地での和食文化が大きく育って、それでもおかしいところがあれば、僕らが現地に出向いて、剪定をすればいいんやないかなと思っているんです。

おおらかにすくすくと、世界中で日本料理の芽が育って欲しい。
アカデミーでも、和食を海外に正しく伝える人材を育てたいと、外国人で和食を学びたい人を招いて、働きながら学べるシステムを構築しています。外国人の日本料理店での就労を、全国で唯一、京都市内に限った特例措置として実現したのは画期的なことやと思いますね。優秀な人材を一人でも多く育てて、和食のタネを世界中に蒔いて欲しいと思っています。
アカデミーの基本方針は、「料理への思いには国境はない」ということ。僕も同じ考えです。
和食も、国境を越えて、広く、新たな道を切り開く時代になったんやと思います。自分の生まれた国で和食をやってみたいという熱意のある人材を発掘し、世界のあちこちでおおらかに、のびやかに、和食の芽がすくすくと育って、大木になってほしいなあと思っています。ゆっくりとその成長を見守って、必要があれば、いつでも植木バサミを持って剪定にいきますよ(笑)
今、世界に広がる和食とその未来を見据えた時、一体、何が大切になるのか。
次回は「和食の未来を切り拓くもの」をテーマにお話したいと思います。

文 郡麻江

■ 菊乃井 本店
京都市東山区下河原町 鳥居前下る下河原町459 八坂通
京都市営地下鉄東西線 東山駅(出入口1) 徒歩12分
京阪本線 祇園四条駅(出入口6) 徒歩14分
075-561-0015
http://kikunoi.jp/kikunoiweb/Honten/index