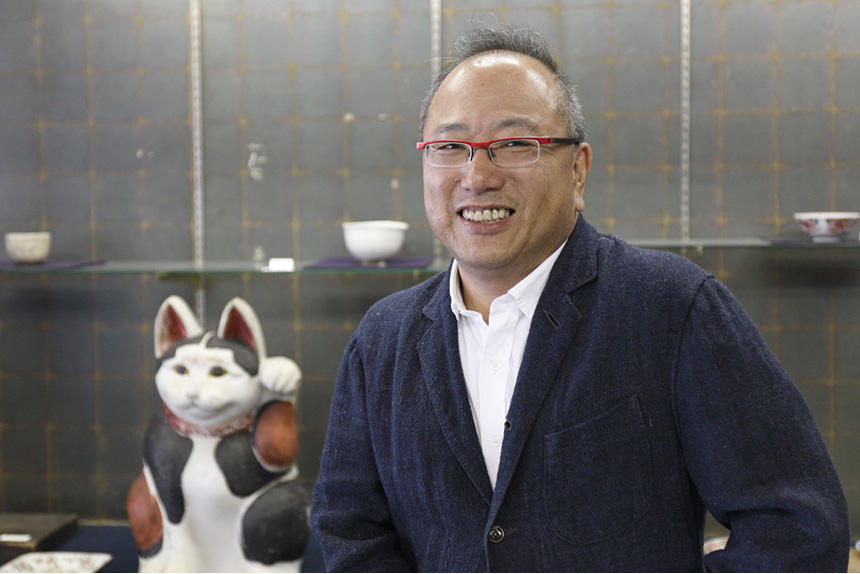うつわと料理は無二の親友のよう。いままでも、そしてこれからも。新しく始まるこのコンテンツでは、うつわと季節との関りやうつわの種類・特徴、色柄についてなどを、「梶古美術」の梶高明さんにレクチャーしていただきます。
梶高明
梶古美術7代目当主。京都・新門前にて古美術商を営む。1998年から朝日カルチャーセンターでの骨董講座の講師を担当し、人気を博す。現在、社団法人茶道裏千家淡交会講師、特定非営利活動法人日本料理アカデミー正会員,京都料理芽生会賛助会員。平成24年から25年の二年間、あまから手帖巻頭で「ニッポンのうつわ手引き」執筆など。全国の有名料理店と特別なうつわを使った茶会や食事会を数多く開催。
十月を茶の湯では「名残り(なごり)の月」と呼んでいます。夏に新茶を収穫し、しばらく茶壺で寝かせておく。十一月に口切り(くちきり)といって、口の封を切って茶壺の蓋を開けます。そして取り出したお茶を石臼で挽き、茶会を催す。つまり、お茶的に暦を考えると、十一月が新年、十月は晦日月となります。晦日月には過ぎた時間を振りかえり、名残りとしての風情をいつくしみ、味わうわけです。
その趣向は、当然、十月に使うお道具やうつわにも表現されます。金継ぎ(きんつぎ)など、丁寧に修理を施したものや、枚数が半端になってしまったうつわなどを、整えたうえで、積極的にお客様のお出しして、あえて趣向として楽しむわけです。
最近、金継ぎを学びたい人に出会うことがままあります。ものを大切に修理して使うことは大変喜ばしいことです。ただ金継ぎというのは、傷を負った箇所を、金と漆を用いて修理するがために、修理箇所を強調してしまうことになります。修理部分に人の注目を集めることは、うつわ全体の持つ印象を大きく変えてしまうことにもなりかねません。
だから金継ぎは、修理跡をさらけ出して、金の力を借りてさらに魅力を加えようとする積極的な修理だと、私は思っています。
古いうつわの修理は、「ものを大切にする」ため「割れて捨てるのはもったいない」からという思いだけ行うのではないと思っています。本来、無傷であり、数もそろっていることが望ましいでしょう。そして、自らの不注意でうつわを破損させてしまった後悔は、形あるものの命を奪ったような罪悪感すら感じます。しかし、しばらくして冷静さを取り戻すと、残された破片たちに未だ魅力がとどまっていることに気づかされます。そこで修理の方法を検討するわけですが、金継ぎはまさにこの傷を思い切って遊んでしまおうという割り切った気持ち持った修理法だと思っています。
私は美術商として長年の経験を重ねてきましたが、以前は欠点にしか見えていなかった修理や品物に刻まれた傷が、今では別の魅力として目に映るようになってきました。
アイドルが年月を重ね、老いという欠点を円熟という魅力に変えて、渋い名優として再評価される姿を見るようです。
料理屋に出向いた際、食材だけでなく器にも名残が表現されていたら、ぜひこの話を思い出してみてください。
わびさびというのは、千利休が完成した茶の湯の精神と言われていますが、利休より約半世紀早く、武野紹鴎はこのわびさびを「冷える」という言葉で表しています。
紹鴎がとらえた「冷える」という意味は、例えば若い茶人がたくさんの道具を抱えて華やかに茶会を開いたとします。するとそれは分不相応な成金的な茶会だと人々の目には映ることでしょう。ところが、年長者が時間をかけて学びながらコツコツと集めてきたお道具で茶会を開くと、人々の尊敬を集めることになるでしょう。
このふたつの違いは、茶会を開くまでに要した時間長さの違いを取り上げていて、選んだ道具を比べて、その評価の違いを問題にしているわけではありません。時間の存在が、お道具をその人にとって分相応なものに変えていく役目を果たすのだと言っているようです。そして、このことを「冷える」という言葉で表現しているのです。
時を経てジーンズの藍がなじんでいくが如く、新しい洋服が時間を経て、その人のスタイルと呼ばれるが如くにになっていく。「冷えていく」ということをそんな感覚で捉えられていたようです。
さてこの10月、名残りの月にこの「冷える」という感覚をテーマに様々なお楽しみをしてみては如何でしょう。古い洋服に腕を通す、食器棚の奥から半端ものの器を取り出して使ってみる、欠けてしまって捨てようかと迷っていた器を修理してみる。少し寂しいような懐かしいような感覚。枯れる前のひと時を愛でるような秋もありだなと私は思います。
今月の器〜冷えたもの〜
名残りの月にふさわしく「冷えたもの」をテーマに、金継ぎの器を選んでみました。器が壊れる原因は、不注意によるものがその大半ですが、古美術の世界では意図的に破損させて、修理を楽しんでいるケースも見受けられます。
これについてはまたの機会にお話しをすることにして。
今月は金継ぎを施された、ふたつのうつわを取り上げています。
古染付双鹿図七寸皿 (1630年代 明)
澄んだ、光沢のあるガラス状の透明釉の下に二匹の鹿、鳥、草花が呉須と呼ばれる藍色の染料によって描かれている、明時代末の1630年頃景徳鎮で作られた、古染付と呼ばれるうつわです。
精密に写生をすることには興味を覚えず、伸びやかにざっくり描くことによって、くずした面白さを強調したようなうつわです。このころは未だ素焼きをする技術が無く、成形し、乾燥させたうつわに、いきなり呉須を使って描いています。まさに鉛筆による下書きの作業を経ずに、すぐに絵筆で描いた小学校に入学して間もない子供たちの絵のように躊躇いの無い絵付けです。スピード感をもった絵付けは、陶芸家と言うよりも、相当に描き慣れた絵師としての技量がある者の手によるのだろうと思います。
それが、400年の時間の中で、誰かが粗相をして割ってしまったのでしょう。金継ぎを施して大切に使ってきたのだと思います。この時代特有の濃紺の染付に、金色がよく映えて、料理を盛っても隠れることのない部位に位置するアクセントになっています。同時に元の所有者のうつわに対する愛情も感じられるようです。
伊万里古九谷様式色絵山水図五寸皿 1640~1690
美しい色彩を使った伊万里古九谷様式の皿です。こちらも整いすぎないところに美があると思います。正確にきっちりと絵を描かず、筆の勢いにのせて描いているように思えところが好ましいところです。絵を見せよう、皿を鑑賞させようと言うのではなく、料理をとの相性を考えて、この程度の完成度に留めてあるのでしょうか。或いは、禅画のようにさらりと描くことで、見る側の自由な想像力に委ねようとしているのでしょうか。絵が強いメッセージを待たない模様であるかのようで、うっかり見過ごしてしまそうです。絵があまりに主張するとそれはもう「うつわ」ではなく「絵」になってしまい、作品として独立し、料理を置いてきぼりにしてしまう。この五寸皿は、余白の取り方といい、絵の重心を皿の中心から左下方にずらして、料理にステージ中央を譲っているところも、うつわとしての役割を理解した憎い演出なのでしょう。
この色絵山水図の皿は、日本でも色絵の生産が始まって、まだ駆け出しの頃のものと言ってよいでしょう。色絵は作り始めたけども、まだ中国からの影響が著しいので、図柄に中国的様式が色濃く残っていますよね。
真ん中の絵を囲む額縁の存在のように紺色の円が描かれています。円の外側は空白のままにして、皿の外周を反り返えらせて、紺色の円と対比するかのように白い円のように見せています。これは鍔型と呼ばれる形状です。古九谷様式、古染付にもよく見かけます。また魯山人もよく鍔型を作品に取り入れています。
写真の皿も、恐らく一部を欠くくらいひどく割ったのでしょう。うつわの割れる形は人の力でコントロールできませんから、割れた形の面白さは、雲の形のように自由奔放です。この皿は修理面積も大きいのですが、お構いなしに金を貼り付けて素知らぬ顔をしているようです。持ち主の細かいことを気に留めない気質の表れでしょうか。この修理箇所に模様を描いても面白いでしょうね。
美しいのだけれど、整い過ぎておらず、おおらかさや勢いをも同時に持ち合わせて、まさにその時代や、その作者にしか生み出せない古いうつわの持つ魅力。そこに後世の者が金継ぎという修理を施す。これって決して許されることのない文化財への落書きのようなことではありませんか。割れた筋に沿って金を貼り付ける以上に、好きな線を描き、模様を施すことも自由自在なのです。そして、また古いうつわに「いま」が新たな味わいとなって加えられるのです。古いうつわに「いま」の持ち主の思いを刻み込む。そしていずれ、また誰かの手に渡って行くのです。今、あなたが手にしているうつわも、そうしてここに辿り着いたもの。長い時を経て独特の味わいを醸す、こういったうつわこそ、「冷えたもの」の真髄をよく表していると思います。うつわのキズも修理もこの秋「名残り」として味わってみましょう。
次回も引き続き「冷えたもの」のお話をしたいと思います。今度は「粗相して」壊れたものでなく、「あえて」、もともと壊れているもの、半端なものを集めて愛でるというあたりから、「冷えたもの」の別の側面をご紹介したいと思います。
■ 梶古美術
京都市東山区新門前通東大路西入梅本町260
075-561-4114
営10時~18時
年中無休(年末年始を除く)