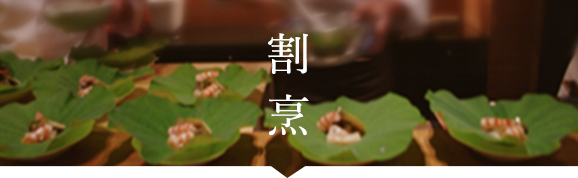京都を代表する和食の料理人に、和食の範疇を飛び出した奇想天外な一皿を作っていただく【割烹知新】。今回は、「祇園 楽味」水野隆弘料理長の「鮎のお番茶揚げ」をご紹介します。
奇想の一皿「鮎のお番茶揚げ」
鮎の唐揚げをお番茶の香りとうるかのソースで
水野隆弘(ミズノタカヒロ)さんは岐阜県出身。名古屋のホテル内和食店で勤めた後、「祇園 さゝ木」に入店。以来15年間、佐々木浩さんの薫陶を受け、右腕といわれるまでになりました。3年前からは姉妹店「祇園 楽味」の料理長として腕を奮っています。
「祇園 楽味」は、その時々の旬の食材を客の好みの味に仕立てる割烹形式の店。美味しいものを知りつくした食道楽が通うことでも知られる店です。

発想秘話
鮎といえば塩焼きが定番。「祇園 楽味」に来店されるお客様のなかには、鮎の季節に何度も「塩焼き」を召し上がる方もいらして、なんとかほかに名物になるような料理をつくれないかと常々考えていました。頭なのなかには、本店の「祇園 さゝ木」で出す「子持ち鮎の唐揚げ」も浮かんでいましたが、同じものでは芸がない(笑)。そこで思いついたのが、常備菜として作られてきた伝統の味「鮎のお番茶煮」と合体させることでした。
鮎をいったん唐揚げにした後、番茶の香りを燻らせ付ける。鮎の特徴ともいえる肝はいったん取り出してうるか(内臓の塩辛)のソースにし、香りをつけた鮎の腹にもどすという料理。独特の肝の苦味や泳ぐような姿はそのままに、サプライズのある料理に挑戦しました。

鮎を開いてはらわたを取り出し、うるかにしておきます。そのうるかにたっぷりの昆布と昆布だし、オイスターソース、実山椒を加えてミキサーにかけます。昆布を加えることで厚みのある旨味とねばりがでる。オイスターソースでコクを、実山椒で爽やかな辛味を添えた、鮎風味のソースになります。だしはもちろん「さゝ木」特製の味です。

開いたお腹がつかないよう、クッキングペーパーを挟んで串をさし、表面に米粉を付けて揚げていきます。うちでは、唐揚げは小麦粉ではなく米粉。よその店では何粉を使っているのか知らないんですが(笑)。とにかく、米粉はカラッと揚がって食感がいいんです。

中華鍋にアルミホイルを敷いて番茶を置き、網に鮎を並べて蓋をする。いわゆる燻製ですね。燻らせるのは1分くらい。身に熱が入りすぎると締まってしまいます。

最後に、串を抜いてペーパーをとりだし、開いたお腹にうるかのソースを入れたらできあがり。見た目は普通の唐揚げだから、一口食べると「何か違う?」と驚きがあります。サクサクの皮にしっとり柔らかな身、噛むとうるかのソースの旨味やコクや辛味が広がる。そして最後にお番茶の香りが鼻に抜けていく。そのまま揚げるのとはまた違う美味しさがあります。

この企画を依頼されたとき「和食から離れてもいい」と言われました。けれど考えれば考えるほど、洋食ではなく伝統料理に想いが向いてしまいました。まさに温故知新です。
旬の時季の鮎は、シンプルな塩焼きも抜群ですが、香ばしくふくよかな味わいのこの鮎料理もぜひ食べていただきたい。家庭でつくってみるのもいいかもしれません。

■ 祇園楽味
京都市東山区祇園町南側570-206
075-531-3733
営17:30~23:00L.O.
休 日曜、第2・4月曜