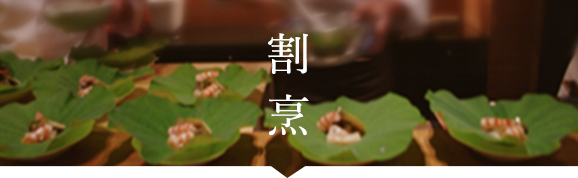京都を代表する和食の料理人に、和食の範疇を飛び出した奇想天外な一皿を作っていただく【割烹知新】。今回は、「上賀茂 秋山」秋山直浩さんの「子持ち鮎のリゾット風」をご紹介します。
奇想の一皿「子持ち鮎のリゾット風」
北山の麓、囲炉裏のある古民家で「この土地ならではの料理」に挑戦し続ける秋山直浩さん。毎朝、鷹峯「樋口農園」まで足を運び、畑と対話しながら料理の構想を練る秋山さんのお料理は、年月とともに幅を広げ、多くの人を魅了し続けています。

発想秘話
うちでは「だしもん」にもち米をしのばせることがままあります。もともとは「だしがもったいないからパンが欲しい」というお客様の声がきっかけでした。今回の「リゾット風」というアイデアも、そこに由来したものです。
鮎については、時期的にそろそろ塩焼きにも飽きてきたので、干物にしたらどうかなと。その場合、子や内臓は塩漬けにして「うるか」にするのが一般的ですが、今回は一度外した「子」を再び鮎に戻し、一緒に食べてもらいます。
外した子を再び鮎に戻すためには、なにか別の食材と合わせて練りこむ必要がある。そこで登場するのが、秋の味覚でもあるさつまいもです。秋になって子を持つようになると、鮎の味はどうしても落ちてくる。子に栄養を取られますから。鮎の味を補う意味でも、さつまいもの甘みは効果的ですね。魚の子って、加熱すると食感が「もそもそ」するじゃないですか。僕は「もそもそ」した食感があまり好きじゃないので、裏ごししたさつまいもと合わせることで、食感を滑らかにするという効果も狙いました。では調理していきましょう。

鮎を開いて中骨を外し、昆布だしに塩と酒を加えた「たてじお」に漬け込んで味をなじませます。それを一夜干しにしたものがこちらですね。ここに、鮎の子を混ぜたさつまいもを挟みこんでいきます。

鮎の子はぷちぷちとした食感が残るぐらいにさっと湯がき、裏ごしたさつまいもと合わせます。味付けには鮎の魚醬を使いました。何か食感を足したかったので、さっと湯がいたレンコンも一緒に挟みます。

それでは炭火で焼いていきましょう。強火の遠火でじっくり30~40分くらい。頭にしっかり火を通したいので、焼き時間は長めです。

だしは、かつおと昆布でとっただしに、鮎だしを加えたダブルスープです。鮎から外した中骨を利用して、鮎だしを用意しました。炙って香ばしくした中骨から煮出したものです。

リゾットには鮎のほかに、合わせだしで炊いたサトイモ、千切りにした生のじゃがいも、ずいき(サトイモの上の部分)が入ります。実はこれ「芋尽くし」なんですよ。僕はこういう「〇〇尽くし」が結構好きなので、今回は芋でまとめてみました。
ずいきは葛をまぶしてから葛湯で湯がき、氷水で冷やしたもの。こうするとちょうど「じゅんさい」のような、ヌルシャリっとした食感になる。生のじゃがいもはスープの熱でレアっぽさを残して......ひとつのお皿の中で、いろんな食感を楽しんでいただきます。

さあ、鮎が焼きあがりました。もち米と芋尽くしの具、鮎が入った器にスープを張り、刻んだ蓼と茗荷を乗せて完成です。

まず鮎を頭からかじってもらいます。スープでやらかくなる前に。身はそのままかじってもいいんですが、ほぐしながら食べすすむと子がスープに溶け出して......リゾットみたいになるでしょう? ちなみにその蓼は僕が鴨川の上流で摘んできたものです(笑)。いろんな食感を楽しみながら、スープに溶け出した鮎のうまみを味わい尽くしてください。

もともと「この立地でしかできない料理が作りたい」という思いがあり、上賀茂で店を始めました。今でも毎日、市場の帰りに樋口農園さんに顔を出します。畑の様子を見ながら料理の構想を練るんです。聖護院かぶらはまだちっさいから、くたくたに炊いて鍋にしようか、とか。菊菜がこれくらいに育ってきたから、来月は菊菜のしゃぶしゃぶにしようか、とか。この場所で店を開いて13年。人手も増えて、徐々にできることが増えてきました。今回の干物もそう。ずっとやりたいという思いはあったけど、手が足りなくてできなかったことのひとつです。この素晴らしい環境で、これからもどんどん「やりたいこと」を実現していきたいですね。
撮影 鈴木誠一 取材・文 鈴木敦子



■上賀茂 秋山
京都市北区上賀茂岡本町58
075-711-5136
12:00~14:30(入店12:30)、18:30~22:00(入店19:30)
休 水曜、月末の木曜