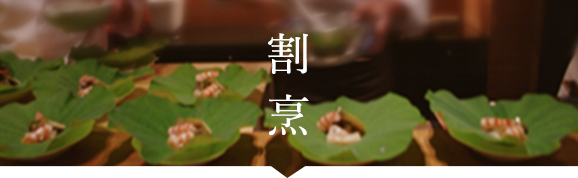京都を代表する和食の料理人に、和食の範疇を飛び出した奇想天外な一皿を作っていただく【割烹知新】。今回は、「祇園 いわさ起」岩﨑道一さんの「テールシチューの白味噌仕立て」をご紹介します。
奇想の一皿「テールシチューの白味噌仕立て」
「祇園 丸山」で料理長を務め、2016年に自身の店「祇園 いわさ起」を開いた岩﨑道一さん。花街・祇園らしい華のあるお料理は、オープン間もなくミシュランで星を獲得するなど、各方面から高い評価を受けています。日本酒はもとより「シャンパーニュに合う」と評されることも多い、いわさ起流。その奇想の一皿をご覧ください。

発想秘話
今回の料理は、フレンチの定番「牛ほほ肉の赤ワイン煮」からヒントを得ました。食べながら「これを赤味噌で炊いたらどうやろ?」と思い、まずはテールを赤味噌で炊いたものを作ってみました。僕は普段から牛テールやほほ肉をよく使うんですよ。京料理というと魚のイメージが強いと思いますが、実は肉を食べたいというリクエストが意外と多くて...。たくさんはいらないけれど、どこかで"ちょっと"お肉も挟みたい。そんな声に応えるために、いろんな形でお出ししています。
ただ、お出汁も一緒に味わうなら、赤味噌より白味噌のほうがいいんですよね。白味噌は味噌そのものにクリーミーさがありますが、赤味噌はさらっとしているので、例えば裏ごししたじゃがいもの餡をかけるとか、そういう工夫がないとおいしくない。白味噌のほうが脂身との相性もいいですしね。
そんなわけで、今回はテールを白味噌のスープで煮込んでみました。テールスープといえば焼肉店の定番ですが、それとはまったく風合いの違う、うちらしい一品に仕立てたいと思います。

まずは牛テールをほろほろになるまで炊いていきます。2回くらい煮こぼしたあと、水を換えて昆布、酒、ねぎ、生姜と一緒に5時間くらい。アクと脂を取りながら、じっくり炊きます。その後、バランスのいい「山利」さんの白味噌を溶いてさらに1時間。これでテールにしっかり味が入ります。ポイントは、テールスープに和のだしを加えた「ダブルスープ」を使う点。テールスープを一番だしで割ることで、とても上品な味わいになります。

やわらかく煮込んだテール肉を骨から外します。長時間じっくり煮込んでいるので、簡単に骨から離れます。

今回一緒に合わせるのは海老芋とはくさい菜です。それぞれお出汁で炊いたものを事前に温め、テールと一緒にココット鍋に盛り込んで火にかけます。海老芋の代わりに丸大根、はくさい菜の代わりに水菜、菊菜、モロッコインゲンなど使ってもおいしいですよ。

陶器の器ばかりじゃおもしろくないので、今日はココットを使ってみました。これは南部鉄器のココットです。直火でぐらぐら煮立てますが、南部鉄器は熱を保存しないので、火から下ろすとすぐに落ち着きます。

仕上げにねぎと辛子を乗せて完成です。柔らかく煮込んだテールは臭みもなく、白味噌のスープとよく合うでしょう? うちの料理はシャンパンとの相性を意識していて、例えばおひたしに柑橘の果汁を搾ったり、お造りに塩レモンやごま油を添えたりということをよくやります。酸味やコクを加えることで、シャンパンやワインとも合いやすくなる。僕自身が好きということもありますが、やはり祇園町の華やかなイメージとシャンパンって相性がいいと思うんです。コースの最初から最後までシャンパンで通しても違和感なく楽しめる、そんな料理が提案できたら素敵かな。

京料理とそうでないものの境界線を一言で定義するのは難しいですが、やはり「ライン」というのは存在すると思います。例えば今回の料理でしたら、赤ワイン煮込みを赤味噌煮込みにしたら京料理になるのか? といえば、そう単純なものでもない。新しい要素を取り入れたあと、それを自分なりに解釈して、どう昇華させるか。いかに「京料理」として納得してもらえるものに仕立てるか。そこが腕の見せ所であり、各々の力量が問われるところじゃないでしょうか。洋食、フレンチ、イタリアン、パティスリー......和食以外のお店でヒントをもらうことも多いですし、勉強会や食事会、他ジャンルの料理人さんとの交流を通して、今後も自分の料理をブラッシュアップしていけたらいいなと思います。
撮影 鈴木誠一 取材・文 鈴木敦子

■ 祇園 いわさ起
京都市東山区祇園町南側570-183
075-531-0533
11:30~14:00入店、17:30~20:00入店
不定休