うつわ知新
うつわと料理は無二の親友のよう。いままでも、そしてこれからも。新しく始まるこのコンテンツでは、うつわと季節との関りやうつわの種類・特徴、色柄についてなどを、「梶古美術」の梶高明さんにレクチャーしていただきます。
-

BLOGうつわ知新
2020.01.28
2月節分
梶高明梶古美術7代目当主。京都・新門前にて古美術商を営む。1998年から朝日カルチャーセンターでの骨董講座の講師を担当し、人気を博す。現在、社団法人茶道裏千家淡交会講師、特定非営利活動法人日本料理アカデミー正会員,京都料理芽生会賛助会員。平成24年から25年の二年間、あまから手帖巻頭で「ニッポンのうつわ手引き」執筆など。全国の有名料理店と特別なうつわを使った茶会や食事会を数多く開催。2月節分2月といえば節分。ところが節分というのは、本来季節の境目を指すため、年に4回あります。節分の中で2月の節分がとりわけ大きな行事として、取り上げられているのは、お正月(旧暦)に近い時期であったということと、人々の春を待ち望む心が他の季節よりも強いからだと思われます。私は八卦見が好きで、時々占ってもらいます。その八卦見の世界で「来年からは...」と言われた場合、それは往々にして1月1日(新暦)からを指すのではなく節分以降を指します。私は毎年京都大学横の吉田神社に節分詣をいたしますが、確かにこの時期は一年で一番冷え込みます。それ故に、節分の翌日が立春の日に決められていることに「なるほど」と大きく頷くばかりです。以前、裏千家14世淡々斎の自画賛の掛軸を所有していたことがありました。そこには一輪の侘助の絵が墨で描かれ「清娯」の文字が添えられていました。厳しい季節の中、真っ先に花を開いたその侘助が春を告げるのを感じ取って気持ちがほんのりと和らぐ様子が表現されたような掛軸でした。2月はまだ春を強く感じることはできなくても、春へ向かう静かな足音が聞こえ始めるまさに「清娯」の季節なのです。伊万里青手古九谷様式 椿平鉢侘助は椿の仲間です。同じように椿を描いたうつわを2種ご紹介させていただきます。ひとつ目は「伊万里青手古九谷様式 椿平鉢」で、1650年前後に作られた作品です。赤を使わず緑を主体にしてデザインされた鉢です。日本人は昔から緑を青と呼ぶ習慣を持っていましたから、緑手ではなく青手と呼ばれてきているのでしょう。このうつわの製作年代はまだ素焼きの技術を持っていませんでしたから、いきなりの筆入れでここまでの作品に描きあげるためには、職人にしっかりした絵の技術が必要でした。その技術の確かさによって、写実的な重く堅苦しい絵にならず、崩しすぎた下手な絵でもない、うつわに最適なバランスの絵に仕上がっているのでしょう。青手と言われるうつわは、伊万里の良質な硬く白い磁器質の磁胎を用いておらず、あえて半磁器のくすんだ色の磁胎を用い、緑や黄色や紫といった鮮やかな色のガラス釉を使いながらも、磁胎のくすんだ色を背景として利用して、鮮やかさではなく、重厚感を醸し出すことに成功しています。半磁器の欠点を逆手にとった企画力と、画質の落としどころの絶妙さなどおよそ400年前の物とはとても考えられません。吉田屋 松竹梅 見込椿 茶盌次にご紹介するのは「九谷吉田屋窯 松竹梅見込椿茶盌」です。先に紹介した「伊万里古九谷様式」の鉢は、つい近年まで石川県加賀地方で製造されたものと考えられ「古九谷」と呼ばれていました。しかし発掘と研究の末に、今は九州の有田地方で焼かれた伊万里の一分野に分類されています。ところが奇妙なことに、19世紀の加賀地方に住んでいた人々は、「青手古九谷」は地元で生産されたと信じていたようで、この「青手古九谷」を今一度復活させたいと1824年に吉田屋窯を立ち上げ、7年間だけではありましたが、さまざまな作品を残しているのです。九州の伊万里では莫大な数の製品を残しながら、ほぼ茶道具を生み出すことはありませんでした。ところが、この吉田屋においては香合、蓋置、水指、茶盌など多様な茶道具も手がけました。吉田屋では青手古九谷での再興を目標に掲げてはいましたが、写しと呼ばれる同一デザインの作品を造ることはせず、全て独自のデザインで作られています。今日、金沢周辺を旅して、九谷焼を求めると、その中にはこの青手古九谷、吉田屋の流れをくむ作品に出会うこともあるでしょう。古九谷が伊万里に分類されてしまっている現代でもなお、多くの北陸の人々にとって古九谷が自分たちの文化の誇りであり続けていることが理解できるでしょう。乾漆 鬼面今でも節分には豆まきをされるお宅もあることかと存じます。これは、春を迎える前に追儺(ついな)と呼ばれる邪気を祓う儀式に代わるものです。それは桃の木で作った弓に、芦の矢をつがえて邪気という気配に立ち向かっていました。やがて邪気が目に見える鬼として表現されるようになり、弓矢を「射る」という言葉の類似性から、「炒った」豆が用いられるようになり、鬼に向かって豆を投げるという形になったわけです。ここでご紹介しているのは、乾漆の鬼面です。乾漆とは麻布や和紙を漆で張り重ね、漆と木粉を練り合わせたものを使って造形を行う技法です。木彫とは異なる造形の自由さが表現できます。鬼面は邪気を具現化したものでもありますが、同時におどろかせて邪気を遠ざける役目で用いられることもあります。日本人は柔軟な解釈で鬼と接しているわけです。原田宰慶作 木彫懸想文像ここでもうひとつご紹介したいのは「原田宰慶作 木彫懸想文像」です。水干(すいかん)という衣装に覆面で顔を隠した人物がいます。肩に梅の枝を抱え、その梅の枝には懸想文(けそうぶみ)がくくりつけられています。この懸想文というのは今で言う恋文のことです。麗しい女性に思いを寄せながらも、その心を打ち明けることのできない男性は、恋文にその思いを託そうとするのですが、昔は 誰もが文字を書けるわけではなく、その代筆業として、下層の公家衆が、内職として人目をはばかり、顔を隠して請け負っていたのです。その懸想文が、やがて神社のお札のような形に発展し、節分の日にこの水干姿で懸想文を売り歩く風習となったようです。現在でも京都の左京区聖護院の須賀神社でその姿を見ることができ、お札を買うこともできます。懸想文は、それを手に入れた女性が大切に化粧箱の中にしまっておくと、美しさが保たれ良縁が来るものと考えられていました。また、衣装箪笥にしまっておけば、着るものに困らないとも考えられていました。私のお知り合いもこの懸想文を手に入れて間もなく、お嬢様に良縁が到来した方があり、情報提供した私はずいぶん感謝されたことがありました。二八(にっぱち)の2月、8月と言えば、商いも薄く静かで地味な季節と思われていますが、春には間があるものの、人々が春を心待ちにする期待感に溢れた季節として捉えられていることがお分かりいただけたかと思います。■ 梶古美術京都市東山区新門前通東大路西入梅本町260075-561-4114営10時~18時年中無休(年末年始を除く)
-

BLOGうつわ知新
2019.12.31
晴れの日にふさわしいお軸と器
梶高明梶古美術7代目当主。京都・新門前にて古美術商を営む。1998年から朝日カルチャーセンターでの骨董講座の講師を担当し、人気を博す。現在、社団法人茶道裏千家淡交会講師、特定非営利活動法人日本料理アカデミー正会員,京都料理芽生会賛助会員。平成24年から25年の二年間、あまから手帖巻頭で「ニッポンのうつわ手引き」執筆など。全国の有名料理店と特別なうつわを使った茶会や食事会を数多く開催。一月格別な、寿ぎの日。新春の喜びに満ちる、晴れの日にふさわしいお軸と器迎春の晴れやかな日を祝うおめでたいお軸「かくて明けゆく空のけしき きのうにかわりたりとは見えねど ひきかへめずらしきここちぞする」と兼好法師は徒然草の中でお正月をこのように読みました。今の言葉で語ると「こうして明けてゆく空の景色は 取り立てて昨日と違っている様子はないけれど うってかわって心新たな心地がする」ということのようです。私たちのお正月は「NHK紅白歌合戦」が終わって、「ゆく年くる年」の番組を見ながら、時報が12時を告げるのを待つ。ただ時報によって年が明けたことを知るだけのことですが、それだけのことでも何かめでたい気分になれる。それほどお正月っていうのは、特別なことなのですね。前回にもお話したように、以前の日本人は12月13日の「事始め」の日に、年末のご挨拶を終えたのを合図に、新年を迎える準備を始め、その作業をこなしていく中で新年への期待感を高めていったのでしょう。そして時計の時報で年明けを知るのではなく、夜が明けるのを見ながら、年が明けた喜びに満たされたのです。時間に追われて余裕のない暮らしの中にいる私は、優雅さとは程遠い年の瀬を送っています。苦手な掃除をして、神棚を整え、玄関にしめ縄を飾り、床の間に飾る掛軸を選ぶという作業を大晦日の夜までかかって、どうにか終えています。お正月を迎える準備の中で掛軸を選ぶと書きましたが、商売柄、私はいくつか正月の掛軸持っています。売り買いを繰り返すので、決まった掛軸はありません。他人に「イマイチ」と言われても、そんなのは私個人の趣向だからお構いなしだと開き直って、あれこれ楽しんで選んでいます。 それでは私がいま所有しているお正月に良さそうな掛軸をご紹介しましょう。「松竹梅雙寿図」まずは、浮田一蕙筆「高砂松竹梅図」三幅対です。三幅の掛軸を同時に飾るわけですので、なかなか普通のお宅ではおさまりきらないサイズではありますが、逆に言えば大画面の迫力は他に代えがたいものがあります。この浮田一蕙は、復古大和絵派の画家として名高く、私も大好きなひとりですが、その穏やかな作風とは裏腹に、強い信念を持った人であったようです。時代は幕末、日本国中で佐幕開国だ、尊王攘夷だと叫びあい、国を二分した激動の時代。その大きなうねりは政治だけにとどまらず、文化芸術にまでもその影響を及ぼします。もはや形骸化し、魅力を失いつつあった大和絵派においても、その画風の再構築が叫ばれていました。一蕙は、そんな絵画の世界でも政治の世界でも改革派の先方として活動をしたため、安政の大獄時には投獄されてしまったほどです。そんな情熱と裏腹に、この三幅対には、みずみずしい常緑の松、天に向かって真っすぐに伸びる潔い竹、寒中にあって香り高い花を咲かせる梅として、好まれた歳寒三友の松竹梅をえがいています。さらに中央には、相生の松の化身(二本の松でありながら根が一つで、共に老いる松)とされる、高砂の尉(じょう)と姥(うば)を描き、夫婦が仲睦まじく添い遂げていく姿を描いています。ただめでたいだけでなく、正月らしい特別感のあるめでたさを描き出しています。写真ではこの三幅対の持つ力強さを十分にお伝え出来ないことが残念です。「赤の一」次にご紹介するのは須田剋太筆「赤の一」です。先にご紹介した掛軸の持つ古典的な雰囲気とは打って変わって、現代の感性を持った掛軸です。須田剋太は司馬遼太郎の紀行文集「街道を行く」の挿絵をつとめ、脚光を浴びた画家です。しかし、彼の遺した書は、彼の描いた力強い絵にも勝るほどの高い評価を得ています。この「赤の一」は1990年に彼が亡くなる半年前に描かれたもので、渾身の作と言っても過言ではありません。「一」は物事の始まりの「一」という意味や、「万法一に帰す」という、万物の根源であるという意味を持っている字です。単純な一本の線ではなく、字に強いエネルギーを込めた作品だと思います。この掛軸も、ただ墨で描いた一ではなく、鮮やかな赤を背景にした一ということで、まさに正月らしいめでたさも表現していると思います。ご自宅で掛軸を鑑賞することができなくても、新年になれば初釜茶会、美術館や博物館の新春企画、またお料理屋さんなど、掛軸を鑑賞できる場所はたくさんあります。誰の作品で、なぜ正月の掛軸として選ばれたのかなどを探ってみると、より深く美術を楽しんでいただけることでしょう。 またその際に、なぜ松竹梅がめでたいのかという理由に触れましたように、何故めでたいのかという理由を深掘りして見ると、美術の背景にある文化を読み解くきっかけになることでしょう。器に見る吉祥十六代 永樂即全作 仁清写 双鶴向付日ごろ何気なく見過ごしていても、うつわの形や図柄には基本「めでたい」が表現されていることはお気づきのことと思います。でも正月はその「めでたい 」の中にもさらに強調された感じが欲しいものです。そこで取り上げるのが 16代永楽即全作仁清写双鶴向付です。菱鶴と言われることもあるうつわです。では鶴はどうしてめでたいのでしょう。「鶴は千年、亀は万年」と言われるように長寿のシンボルとされてきたこと。そして鶴は樹齢千年を経た松に宿る特別に気高い鳥であること。更に双鶴は、その生涯を同一の雌雄で添い遂げるということがその理由であるようです。また菱型が意味する菱という植物は、その繁殖力の強さから子孫繁栄を意味するのです。とどめにうつわの色を赤くすることでめでたさを際立たせてもいるわけです。これだけめでたさを重ねたうつわでお料理が出てくれば、さすがに新しい年はきっと良い年になりそうですよね。ところが、めでたさも度を超えると、正月や特別な機会にしか使えないうつわになって、経済性が悪いとご心配の方もあるやもしれません。しかしこの特別感こそが大切だと教えて頂いたことがあります。ある料亭のご主人は「いつでも使えるうつわは、いつも使えへん」。つまり季節感やそのうつわの持つ意味が曖昧なものは、結局お客様にありがた味を感じていただけないからあかんのだそうです。高いお料理代を払って遊びに来たお客様には、存分に遊んで帰ってもらわなあかんのです。鶯宿梅吸い物椀(おうしゅくばい すいものわん) 次はお椀をご紹介しましょう。椀の表裏一面に、さらには高台内にまで、びっしりと梅の花を金蒔絵で描き詰め、ところどころに鶯を宿していることから鶯宿梅(おうしゅくばい)蒔絵吸物椀と呼ばれています。懐石料理の要は煮物椀で提供するお料理です。ですから主役らしく煮物椀は吸物椀に比べると大振りに作られています。それを吸物椀で代用すれば少し窮屈なわけです。その窮屈さは覚悟のうえで、多くの料理人はこの鶯宿梅吸物椀を新春のこの時期の煮物椀として使いたがるほど人気のあるお椀なのです。鶯宿梅にはこんな物語があります。平安時代後期に記された大鏡(おおかがみ)という物語の中で、夏山繁樹(なつやまのしげき)という若侍が語っているお話があります。あるとき、村上天皇がお住まいになる清涼殿と呼ばれる御座所の前の梅の木が枯れてしいました。天皇様は皇室の道具などを管理するお役の蔵人(くろうど)と夏山繁樹に代わりの木を探してくるようにとお命じになられたそうです。苦労の末に、西の京の辺りの屋敷で見つけた梅の木を掘り起こして、清涼殿の前に移植すると、枝に文が括られていることに天皇がお気づきになったそうです。その文には「勅なればいともかしこしうぐひすの宿はと問はばいかが答へむ」と記されていたそうです。その梅の木のあった屋敷の主を尋ねたところ、紀貫之の娘であることが判明し、強引に梅の木を持ち帰ったことを天皇も夏山繁樹も恥ずかしく思ったそうです。歌を現代の言葉で表現すれば「天皇のご命だから畏れ多いことですが、この梅の木にやってきていた鶯が、家がなくなったことを尋ねたなら、私は何と答えてやればよいのでしょうか」いう、何とも洒落たお話がこの模様には添っているのです。庭山耕園 図・川合漆仙 塗 日の出椀さて、最後は日の出鶴の椀をご紹介いたします。漆黒の闇の中から鮮やかな朱の朝日が昇ってくる。その太陽の中で、黄金に輝く鶴が舞う姿を描いています。これこそ元旦の朝に使いたいような特別な意匠です。鶴の絵は明治から戦前にかけて大阪で活躍した四条派の絵師、庭山耕園によるものです。躍動的な鶴の姿が素晴らしい新年の幕開けを予感させるようです。お塗は2代川端近左に学んだ大阪の川合漆仙によるものです。ちょうど図案を手掛けた庭山耕園の展覧会が大阪市立美術館で2019年12月18日(水)~2020年2月9日(日)の期間開催されています。今月も、予定を大幅に超えた長いお話になってしまいました。私たちの暮らしの中にある美をより深く理解し、今よりも楽しむためには、教養というものが欠かせないのだと、この文章を書きながら強く感じています。高慢で鼻持ちならない教養ではなく、子供のような「これなに?あれどういうこと?」という探求心を満たしてやるということです。私も色んな資料片手に、学びながらの寄稿なのです。 撮影/竹中稔彦 聞き書き/郡 麻江■ 梶古美術京都市東山区新門前通東大路西入梅本町260075-561-4114営10時~18時年中無休(年末年始を除く)
-

BLOGうつわ知新
2019.11.30
"冷えたもの"が持つひそやかな"力"
梶高明梶古美術7代目当主。京都・新門前にて古美術商を営む。1998年から朝日カルチャーセンターでの骨董講座の講師を担当し、人気を博す。現在、社団法人茶道裏千家淡交会講師、特定非営利活動法人日本料理アカデミー正会員,京都料理芽生会賛助会員。平成24年から25年の二年間、あまから手帖巻頭で「ニッポンのうつわ手引き」執筆など。全国の有名料理店と特別なうつわを使った茶会や食事会を数多く開催。師走12月。。。。。私たちは明治になるまで数字を用いて12カ月を表さず、その時期の風情に相応しい和名をもってそれを表現してきました。師走は、師と仰がれる身分の高い僧侶でさえも慌ただしく駆け回られる姿を表現したことが「師馳す(しはす)」が語源だと言われているようです。小学校の授業で私の担任が「私たち先生でさえ忙しくする時期だから、師走と言うんだ。」と教わったため、私の頭の中では、お坊さんではなく、未だに小学校先生たちが通知簿の作成や家庭訪問で忙しく走り回っています。幼い頃に植え付けられた印象というのは、フライパンの焦げ付きみたいなもので、いつまでも頭に中に残ってしまうものです。古美術商である私は、茶道・華道・香道など伝統を重んじる世界に関わりが深い職種であるため、師走の13日朝には「事始め」という、いかにも年の瀬らしい行事がございます。私の場合、裏千家のお家元様に出向き、無事に過ごしてきたこの一年の感謝と共に来るべき新しい年を迎える準備を始めさせていただくためのご挨拶をいたします。昔の人たちは、このご挨拶を終えた後、お正月の炊事を行うための薪を取りに行き、門松の準備なども始めたようです。私の住む祇園では、芸舞妓の皆さんがお世話になった方々へご挨拶回りをされるので、なんとも華やかな朝になります。そんな華やかさとは裏腹に、この師走には今で言う「インスタ映えする」ような行事が昔から少なかったためか、この師走の風情を描いた掛軸がなかなか見つかりません。「走り・旬・名残リ」という言葉があります。多くの場合床の間にかける掛軸は、やや季節に先駆けたタイミングで飾り、その風情を心待ちに楽しむ「走り」的な、傾向があります。つまりフライングして楽しむということです。ところが、この師走時期に先駆けて掛軸を選ぶと、年も明けてないのに旭日や朝焼けの赤富士、高砂、萬歳・蓬莱山の絵をお床に飾ることになってしまいます。師走の時期の掛軸とは違って、選ぶ題材に事欠かないのですが、フライングすると、あまりにも大きな違和感があるわけです。ですから師走だけは季節を先駆けての掛軸を飾ることができず、その結果、選ぶことのできる掛軸の選択肢が圧倒的に少ないのです。ですから、私は日ごろから、師走の掛軸を見かけたら極力手に入れるように心がけています。なかなか見つからない師走の掛け軸ですが、やっと見つけたものがあるので、ご紹介させていただきます。絵を江戸初期の狩野派の絵師、狩野長信が描き、その絵に茶人として名を馳せた松平不昧公が、後に歌を添えた掛け軸です。描かれている題材は茶筅売りの姿です。添えられている歌を賛(さん)と言いますがそこには 扣瓢箪念仏(たたくひょうたんねんぶつ)市賣茶筅(いちうるちゃせん)空也々々(くうやくうや)一瓢一筅(いっぴょういっせん)と、松平不昧公の手によって添え書されています。この歌の中に出てくる「空也(くうや)」というのは、今から約1100年前の平安時代中期に生きた空也上人(くうやしょうにん)のことです。空也上人は在俗の修行やとして諸国を巡り、また京のみやこの辻に立って鉦(かね)、あるいは瓢箪を叩いて念仏を唱えて人々の救済を願ったそうです。今も京都の東山にある六波羅蜜寺には、口から小さな阿弥陀仏を吐きながら念仏を唱える空也上人立像が残され、重要文化財に指定されています。空也上人に従って多くの人々が帰依したので、上人が入寂された後も人々は上人を慕って11月13日に空也忌を催しました。そして人々は高らかに念仏を唱え、鉦(しょう)をたたき、竹杖で瓢箪(ひょうたん)をたたきながら年の暮れまで、みやこの内外を回ったそうです。やがてそれが、神社の祭礼に屋台が並ぶが如く、商人たちが物売りをするようにもなり、瓢箪を叩いて空也々々と念仏を唱えながら歩く姿が、この掛軸に描かれている茶筅売りなのです。「うつわ知新」のタイトルをいただきながら、さっぱりうつわのお話しをしないで進めてきました。しかしここで皆さんにお考えいただきたいことは、お料理のうつわは陶器・漆器・ガラス・銀・錫・木で作られたものだけなのでしょうか。お部屋に飾られた掛軸・絵画、あるいはお花・花器といったものたちも、食事をするお部屋の空間を盛り上げるための役目を担うわけですから、広い意味で言えばうつわとも言えるかもしれません。お料理屋さんへ行った時、掃き清めて打ち水をしたお玄関や、迎え入れてくれる暖簾に始まり、今日お話しした掛軸等々に至るまで、すべて皆様のお会計に含まれているものですから、これらを味わうことなく帰ることは実にもったいないことです。ぜひ、目の前に運ばれてくる料理やうつわだけでなく、接客サービスも含めて提供されたすべてをお召し上がりになってください。最後の最後にひとつだけうつわのご紹介もさせていただきます。師走になり、冷え切った空気に背中が丸くなってくると、温かいものが何よりのご馳走になることは今も昔も同じ。千利休の孫にあたる三代目千宗旦(せんのそうたん)が、楽家四代目の一入(いちにゅう)に、柚味噌を味わうために作らせたと伝わるうつわです。その後、代がかわっても「柚味噌皿」と呼ばれ作り続けられている楽家の冬の定番です。アツアツに炊いた大根に柚味噌をのせて、うつわを手で包み込んで、湯気の中でフゥフゥ言いながら、その温かさも柚の香もご馳走にしてしまった400年前の茶人たちの姿が目に浮かぶようです。■ 梶古美術京都市東山区新門前通東大路西入梅本町260075-561-4114営10時~18時年中無休(年末年始を除く)
-

BLOGうつわ知新
2019.10.31
"冷えたもの"が持つひそやかな"力"
梶高明梶古美術7代目当主。京都・新門前にて古美術商を営む。1998年から朝日カルチャーセンターでの骨董講座の講師を担当し、人気を博す。現在、社団法人茶道裏千家淡交会講師、特定非営利活動法人日本料理アカデミー正会員,京都料理芽生会賛助会員。平成24年から25年の二年間、あまから手帖巻頭で「ニッポンのうつわ手引き」執筆など。全国の有名料理店と特別なうつわを使った茶会や食事会を数多く開催。"冷えたもの"が持つひそやかな"力"先月「冷えたもの」というテーマでお話ししましたが、破損した器だけでなく、半端になったうつわたちも、この「冷えたもの」の仲間に入れることができるでしょう。私たちはうつわを求めるときに、5客、あるいは10客揃ったものを買い求めてきました。ところが、揃っていたはずのうつわも、残念なことに、やがてその数を減らして、揃わなくなります。すると私たちは、それを半端物として食器棚の奥に片付け、あるいはお客様へは出さないうつわとして扱うようにさえなってしまいます。でも、うつわ自体がその魅力を失ったわけではありません。ですから昔の数寄者たちは、こういった半端物にあえて出番与えることを考え出したのでしょう。これが、秋の10月、「名残り」の月なのです。傷ついたもの、半端物のリバイバル月です。さらに数寄者たちはそれだけに留まらず、この「半端物」を積極的に作り出し、色や形の異なるバラバラのうつわで5客、10客を揃えて楽しむ「寄せ向(よせむこう)」を考え出し、陶工たちに作らせたのです。こうして、意図的に「冷える」を作り出してまで楽しみだした彼らの遊びは、「呼続(よびつぎ)」と言う新しい発想をも生み出します。破損して失われたうつわのパーツを、従来は漆を用いて修復修理していたところを、別の焼き物の破片で補う「呼続」という方法を考え出します。「呼続」には似通った質の焼き物を用いることもあれば、あえて異なる質や色の焼き物を当てはめて、うつわの再構築を遊んでしまうようなことさえあります。挙句の果てに数寄者たちは、「呼続」をせんがために、意図的にうつわを割っていることさえあります。まるでジーンズを、破き、つぎはぎし、ストーンウォッシュし、漂白して、なんでもありの加工を施して着こなしてしまう現代人のようです。いま私の手元に、北大路魯山人が作った織部十字皿が数枚あります。それらは、焼成時に窯の中で焼け縮むことが上手くできなかったためか、あるいは作られた時の形を維持できないほど反ってしまったために完全に裂けてふたつになっています。 ふたつになっていなくても、大きなひび割れが入っていたりします。これらは「窯切れ」と呼ばれ、「げもの」として廃棄されることも多く見られます。それでも魯山人はこの「げもの」状態でも、魅力を失っていないと感じたのか、復活させるために再度釉薬を掛けて焼き直した痕跡を残しています。ある日、同業の先輩に、このことを裏付けるような魯山人がうつわを復活させたエピソードをお聞きしました。ある時、京都東山山麓にある裏千家桐蔭席という茶室を魯山人が借りて、展覧会を開いていたそうです。そこへ先輩のさらに大先輩が訪ねて行ったところ、販売されていた作品の脇に窯の中で裂けたと思われる「げもの」が無造作に置かれているのを目にしたそうです。「これはどうしたのか?」と尋ねたところ「不出来な作品であるから売り物にならない。」と魯山人が返答したそうです。そこで、大先輩は金継や焼き直して発表することをためらう必要はないと話したそうです。それ以来、魯山人自らが金継ぎなどを施し、作品を発表するようになったそうです。また、その時のご縁で、次の展覧会は京都美術倶楽部で開かれたとのことでした。 これもまた、「冷えたもの」にまつわるエピソードですよね。「げもの」として生まれた焼物のエピソードを、もうひとつお話しいたしましょう。 古い窯跡の周辺には、おびただしい数の陶片が埋まっていることは、ご存知だと思います。もちろんそれらは文化財として、現在は保護されています。それでも、それらを掘り起こし、商売につなげようという人はまだいるのではないでしょうか。昔、伊万里や唐津の窯跡周辺では、雨が降って、土が柔らかくなった日を狙って、鉄の棒を地面に突き立てて陶片を探したと聞いています。細い鉄の棒は地面に深くに突き刺さり、陶片に当たるとカチッと音を立てて、埋っている場所を教えてくれたそうです。そして掘り起こした陶片を持ち帰り、まるでジグソーパズルをするが如く組み合わせて、元の姿に復元する。ピースがそろわず復元できないものは、他のピースに置き換えて、呼び継ぎをする。そうして復元出来なくとも復活した焼物は、地中で長く留まっていた味わいも加味されて、完品や伝来品とは違った深くて素朴な、まさに「冷えたもの」として力を持つことがあるのです。ごちそうがあふれるこの時代ですが、質素な料理とともににお酒を楽しみたい人などには、この「げもの」が「冷えたもの」としてたまらないお友達になるのでしょう。桃山時代から江戸初期の頃、権力者たちは茶道具収集に夢中になっていました。京都街中の三条通り界隈には、当時「唐物屋」と呼ばれた陶器屋が何件も軒を連ねていたそうです 。唐津や美濃で焼きあがった茶器や食器が大量にここに運ばれ、目利きたちの手によって、店頭に並べるかどうか選別されていたそうです。 ふるいにかけられて、落ちこぼれたものは、近辺にまとめて廃棄されたらしく、その跡地からはおびただしい数の焼き物が発掘されています。それらは現在、京都の西陣地区にある考古資料館に保管展示されています。まさに冷えたものの宝の山です。是非、一度お運びください。今月の器〜冷えたもの〜侘びたという感覚を呼び覚ますような、呼び継いだもの、金継ぎを施したものとして2種の皿を選びました。それぞれ雰囲気は異なるのですが、両方とも、素朴で枯れた料理をちょこっと盛られるのを待っているようです。 壊れたり、捨てられたり、欠点を抱えた状態での再出発。でもその欠点が作られた時代より後世の人の手と感性で見事に復活。そんな苦難を乗り越えた"力"がどこかに潜んでいるようです。 素材を生かした素直な料理を要求してくるような、おおらかでありながらも強い主張が感じられるうつわです。 「冷えたもの」うつわには、素朴な料理をご馳走に変えてしまう力が秘められているのです。唐津線紋五寸皿 (1600年代初頭)シンプルな線だけの装飾が潔さを感じさせる唐津焼五寸皿。このうつわには、焼却時の窯内で重ねて焼いたときの、目跡(めあと)と呼ばれる痕跡が残されています。互いにくっついてしまわぬように、うつわ間に土玉挟んだ痕跡が中央部に残っています。おおきく歪んでしまったためか「げもの」として廃棄されたのでしょう。 それをわざわざ発掘し、呼び継ぎや金継ぎを施したものです。自然な割れや歪みを逆手にとって見どころに変えてしまった感じですね。初期伊万里染付総花紋五寸皿 こちらも窯の中で大きな歪みが生じて捨てられて、土の中に眠っていた初期伊万里の五寸皿です。この皿は、割れたものを樹脂で継いでいます。金継ぎは傷跡に金を載せるため、修復跡を目立たせることで新たな景色を生み出します。こちらはその真逆で、磁器色に近い樹脂を使っています。私もあえて金継ぎはせずに、樹脂で修復し、その後、紅茶に漬けおきして古色らしい感じに仕上げることがあります。金ではなく、紅茶染めでもなく、アクリル絵の具でペイントすることもありですよね。 初期伊万里は高台が小さく、高台周辺は肉厚で、陶工が掴んだ指跡も残されていることもしばしばです。呉須の精製が悪いため、沈んだ染付の色。素焼きの技術がまだ無かったために、シンプルに描き流した模様。本来は美しいはずのない、雑味を持った稚拙さが、このうつわの魅力です。■ 梶古美術京都市東山区新門前通東大路西入梅本町260075-561-4114営10時~18時年中無休(年末年始を除く)
-
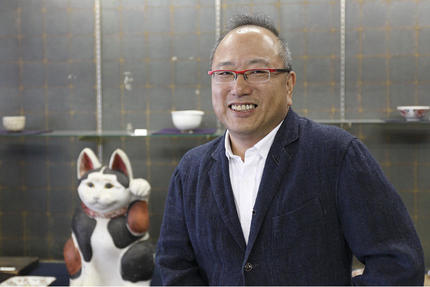
BLOGうつわ知新
2019.09.30
名残りの月にこそ愉しみたい"冷えたもの"
梶高明梶古美術7代目当主。京都・新門前にて古美術商を営む。1998年から朝日カルチャーセンターでの骨董講座の講師を担当し、人気を博す。現在、社団法人茶道裏千家淡交会講師、特定非営利活動法人日本料理アカデミー正会員,京都料理芽生会賛助会員。平成24年から25年の二年間、あまから手帖巻頭で「ニッポンのうつわ手引き」執筆など。全国の有名料理店と特別なうつわを使った茶会や食事会を数多く開催。 十月を茶の湯では「名残り(なごり)の月」と呼んでいます。夏に新茶を収穫し、しばらく茶壺で寝かせておく。十一月に口切り(くちきり)といって、口の封を切って茶壺の蓋を開けます。そして取り出したお茶を石臼で挽き、茶会を催す。つまり、お茶的に暦を考えると、十一月が新年、十月は晦日月となります。晦日月には過ぎた時間を振りかえり、名残りとしての風情をいつくしみ、味わうわけです。 その趣向は、当然、十月に使うお道具やうつわにも表現されます。金継ぎ(きんつぎ)など、丁寧に修理を施したものや、枚数が半端になってしまったうつわなどを、整えたうえで、積極的にお客様のお出しして、あえて趣向として楽しむわけです。 最近、金継ぎを学びたい人に出会うことがままあります。ものを大切に修理して使うことは大変喜ばしいことです。ただ金継ぎというのは、傷を負った箇所を、金と漆を用いて修理するがために、修理箇所を強調してしまうことになります。修理部分に人の注目を集めることは、うつわ全体の持つ印象を大きく変えてしまうことにもなりかねません。だから金継ぎは、修理跡をさらけ出して、金の力を借りてさらに魅力を加えようとする積極的な修理だと、私は思っています。古いうつわの修理は、「ものを大切にする」ため「割れて捨てるのはもったいない」からという思いだけ行うのではないと思っています。本来、無傷であり、数もそろっていることが望ましいでしょう。そして、自らの不注意でうつわを破損させてしまった後悔は、形あるものの命を奪ったような罪悪感すら感じます。しかし、しばらくして冷静さを取り戻すと、残された破片たちに未だ魅力がとどまっていることに気づかされます。そこで修理の方法を検討するわけですが、金継ぎはまさにこの傷を思い切って遊んでしまおうという割り切った気持ち持った修理法だと思っています。私は美術商として長年の経験を重ねてきましたが、以前は欠点にしか見えていなかった修理や品物に刻まれた傷が、今では別の魅力として目に映るようになってきました。アイドルが年月を重ね、老いという欠点を円熟という魅力に変えて、渋い名優として再評価される姿を見るようです。料理屋に出向いた際、食材だけでなく器にも名残が表現されていたら、ぜひこの話を思い出してみてください。 わびさびというのは、千利休が完成した茶の湯の精神と言われていますが、利休より約半世紀早く、武野紹鴎はこのわびさびを「冷える」という言葉で表しています。 紹鴎がとらえた「冷える」という意味は、例えば若い茶人がたくさんの道具を抱えて華やかに茶会を開いたとします。するとそれは分不相応な成金的な茶会だと人々の目には映ることでしょう。ところが、年長者が時間をかけて学びながらコツコツと集めてきたお道具で茶会を開くと、人々の尊敬を集めることになるでしょう。このふたつの違いは、茶会を開くまでに要した時間長さの違いを取り上げていて、選んだ道具を比べて、その評価の違いを問題にしているわけではありません。時間の存在が、お道具をその人にとって分相応なものに変えていく役目を果たすのだと言っているようです。そして、このことを「冷える」という言葉で表現しているのです。時を経てジーンズの藍がなじんでいくが如く、新しい洋服が時間を経て、その人のスタイルと呼ばれるが如くにになっていく。「冷えていく」ということをそんな感覚で捉えられていたようです。さてこの10月、名残りの月にこの「冷える」という感覚をテーマに様々なお楽しみをしてみては如何でしょう。古い洋服に腕を通す、食器棚の奥から半端ものの器を取り出して使ってみる、欠けてしまって捨てようかと迷っていた器を修理してみる。少し寂しいような懐かしいような感覚。枯れる前のひと時を愛でるような秋もありだなと私は思います。今月の器〜冷えたもの〜 名残りの月にふさわしく「冷えたもの」をテーマに、金継ぎの器を選んでみました。器が壊れる原因は、不注意によるものがその大半ですが、古美術の世界では意図的に破損させて、修理を楽しんでいるケースも見受けられます。これについてはまたの機会にお話しをすることにして。今月は金継ぎを施された、ふたつのうつわを取り上げています。古染付双鹿図七寸皿 (1630年代 明)澄んだ、光沢のあるガラス状の透明釉の下に二匹の鹿、鳥、草花が呉須と呼ばれる藍色の染料によって描かれている、明時代末の1630年頃景徳鎮で作られた、古染付と呼ばれるうつわです。精密に写生をすることには興味を覚えず、伸びやかにざっくり描くことによって、くずした面白さを強調したようなうつわです。このころは未だ素焼きをする技術が無く、成形し、乾燥させたうつわに、いきなり呉須を使って描いています。まさに鉛筆による下書きの作業を経ずに、すぐに絵筆で描いた小学校に入学して間もない子供たちの絵のように躊躇いの無い絵付けです。スピード感をもった絵付けは、陶芸家と言うよりも、相当に描き慣れた絵師としての技量がある者の手によるのだろうと思います。 それが、400年の時間の中で、誰かが粗相をして割ってしまったのでしょう。金継ぎを施して大切に使ってきたのだと思います。この時代特有の濃紺の染付に、金色がよく映えて、料理を盛っても隠れることのない部位に位置するアクセントになっています。同時に元の所有者のうつわに対する愛情も感じられるようです。伊万里古九谷様式色絵山水図五寸皿 1640~1690 美しい色彩を使った伊万里古九谷様式の皿です。こちらも整いすぎないところに美があると思います。正確にきっちりと絵を描かず、筆の勢いにのせて描いているように思えところが好ましいところです。絵を見せよう、皿を鑑賞させようと言うのではなく、料理をとの相性を考えて、この程度の完成度に留めてあるのでしょうか。或いは、禅画のようにさらりと描くことで、見る側の自由な想像力に委ねようとしているのでしょうか。絵が強いメッセージを待たない模様であるかのようで、うっかり見過ごしてしまそうです。絵があまりに主張するとそれはもう「うつわ」ではなく「絵」になってしまい、作品として独立し、料理を置いてきぼりにしてしまう。この五寸皿は、余白の取り方といい、絵の重心を皿の中心から左下方にずらして、料理にステージ中央を譲っているところも、うつわとしての役割を理解した憎い演出なのでしょう。 この色絵山水図の皿は、日本でも色絵の生産が始まって、まだ駆け出しの頃のものと言ってよいでしょう。色絵は作り始めたけども、まだ中国からの影響が著しいので、図柄に中国的様式が色濃く残っていますよね。 真ん中の絵を囲む額縁の存在のように紺色の円が描かれています。円の外側は空白のままにして、皿の外周を反り返えらせて、紺色の円と対比するかのように白い円のように見せています。これは鍔型と呼ばれる形状です。古九谷様式、古染付にもよく見かけます。また魯山人もよく鍔型を作品に取り入れています。 写真の皿も、恐らく一部を欠くくらいひどく割ったのでしょう。うつわの割れる形は人の力でコントロールできませんから、割れた形の面白さは、雲の形のように自由奔放です。この皿は修理面積も大きいのですが、お構いなしに金を貼り付けて素知らぬ顔をしているようです。持ち主の細かいことを気に留めない気質の表れでしょうか。この修理箇所に模様を描いても面白いでしょうね。 美しいのだけれど、整い過ぎておらず、おおらかさや勢いをも同時に持ち合わせて、まさにその時代や、その作者にしか生み出せない古いうつわの持つ魅力。そこに後世の者が金継ぎという修理を施す。これって決して許されることのない文化財への落書きのようなことではありませんか。割れた筋に沿って金を貼り付ける以上に、好きな線を描き、模様を施すことも自由自在なのです。そして、また古いうつわに「いま」が新たな味わいとなって加えられるのです。古いうつわに「いま」の持ち主の思いを刻み込む。そしていずれ、また誰かの手に渡って行くのです。今、あなたが手にしているうつわも、そうしてここに辿り着いたもの。長い時を経て独特の味わいを醸す、こういったうつわこそ、「冷えたもの」の真髄をよく表していると思います。うつわのキズも修理もこの秋「名残り」として味わってみましょう。 次回も引き続き「冷えたもの」のお話をしたいと思います。今度は「粗相して」壊れたものでなく、「あえて」、もともと壊れているもの、半端なものを集めて愛でるというあたりから、「冷えたもの」の別の側面をご紹介したいと思います。■ 梶古美術京都市東山区新門前通東大路西入梅本町260075-561-4114営10時~18時年中無休(年末年始を除く)
- ALL
- - 料亭割烹探偵団
- - 食知新
- - 京都美酒知新
- - 京のとろみ
- - うつわ知新
- - 「木乃婦」髙橋拓児の「精進料理知新」
- - 「割烹知新」~次代を切り拓く奇想の一皿~
- - 村田吉弘の和食知新
- - 料亭コンシェルジュ
- - 堀江貴文が惚れた店
- - 小山薫堂が惚れた店
- - 外国人料理人奮闘記
- - フォーリンデブはっしーの京都グルメ知新!
- - 京都知新弁当&コースが食べられる店
- - 京の会長&社長めし
- - 美人スイーツ イケメンでざーと
- - 料理人がオフに通う店
- - 京のほっこり菜時記
- - 京都グルメタクシー ドライバー日記
- - きょうもへべれけ でぶっちょライターの酒のふと道
- - 本Pのクリエイティブ食事術


