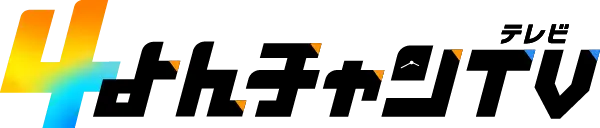2025年10月20日(月)公開
「いとこの戦死が嬉しかった」...軍国少女だった91歳の後悔 市民の間に蔓延した"同調圧力" #きおくをつなごう #戦争の記憶
編集部セレクト
日本が戦争に突き進んだ頃、国威発揚に重要な役割を果たした組織がある。銃後の主婦たちによって作られた、国防婦人会。「国防は台所から」をスローガンに、かっぽう着姿で兵士を見送るなどして、市民を戦争協力へと駆りたてた。 国防婦人会の幹部の娘として育った女性は、当時を振り返ってこう述べる。“いとこの戦死が、嬉しかった“と…。 なぜ、そんな思いを抱くに至ったのか? 当時の社会を覆った“同調圧力“と、戦後80年に女性が抱く“後悔”に迫る。(MBSニュース・萩原大佑)
「♪天皇陛下の御前で 死ねと教えた父母の…」刻み込まれた“軍国主義”

三重県大台町に住む梅本多鶴子さん(91)。太平洋戦争のころは小学生で、地元の国民学校に通っていた。学校で習った歌を、いまでも口ずさむことができる。
「~♪勝ち抜く僕ら少国民 天皇陛下の御前で死ねと教えた父母の 赤い血潮を受け継いで♪~」
「こういう歌を習って、天皇陛下の御前で死ねって、親が教えているわけだから、もうそれが普通やと思っていました」
“天皇の前で死ぬことを父母が教えた”という、強烈な歌詞。当時、子どもたちは天皇に仕える小さな皇国民=「少国民」と呼ばれ、徹底した軍国教育を受けた。
日本は必ず戦争に勝つ。そのために命を捨てることもいとわない__ 梅本さんも、こうした思想を叩きこまれ、自然に軍国少女のひとりとなっていった。学校の友人、先生、自分のまわりの誰もが、同じ考えだと信じていた。
国防婦人会 戦争協力にのめり込んだ主婦たち

軍国主義は学校だけではなく、家庭にも侵食していた。梅本さんの母・いとのさんは、地域の「国防婦人会」の幹部だった。梅本さんは、戦争協力に前向きだった母の背中を見て育った。
国防婦人会は、満州事変の翌年、1932年に大阪で発足。「国防は台所から」をスローガンに、出征兵士の見送りなどを通じて、主婦たちを戦争協力へと駆りたてた。日中戦争、太平洋戦争と戦線が拡大するに従って会員の数は増え、やがて1000万人規模に膨れ上がった。
梅本さんの母・いとのさんは、地域の農作業の手伝いをしたり、戦地の兵士に送る慰問袋を作ったりするなど、寝る間も惜しんで国防婦人会の活動に邁進した。梅本さんはそんな母の姿を、誇らしく感じていたという。
「なかなか国防婦人会は威厳があってね。どこへ行っても意見が通るというかな、役場とか学校とか、そういう所へ出向いていた」
「(母は)国防婦人会の偉い人。村長さんよりも威厳があったような感じ」
女性には、結婚して夫の「家」に入って家事や育児をすることが望まれ、参政権も認められていなかった時代。国防婦人会の活動は、女性が社会に出て男性と同じように振る舞える数少ない機会でもあった。
参加した女性たちが、喜びや、やり甲斐を感じていた一方で、婦人会を監督下に置いた軍部の狙いは、“夫や子が戦死したとしても反戦感情を抱かないように女性たちを教育すること”にあったとされている。
「あんたは一人前じゃない」息子いない母がかけられた言葉

国防婦人会の活動に積極的に参加していた梅本さんの母・いとのさんだったが、その立場は決して“盤石”ではなかった。
ある日、婦人会の活動から帰ってきた母が、いつもとは違う暗い表情で漏らした言葉を、梅本さんは今も忘れられない。
「男の子がないばっかりに、“一人前でない”と。(子どもを)兵隊に出していないから国のお役に立っていない。どんな話をしても、“あんたは一人前でない”と(母は)言われてね」
梅本さんの家族は、姉妹3人と両親。息子2人は幼いころに病気で亡くなり、梅本さんの父親も年齢の事情で召集されなかったため、戦地に出征する男子がいなかった。
当時、戦争の長期化に伴って多くの兵士が必要とされた中で、女性には、男子を産み育てて、兵士として国に捧げることが強く求められていた。戦争に息子を出すことがお国のため、それが「一人前」とされたのだ。
“息子がいない分、婦人会の活動でお国のためになろう”と、母は考えたのではないか__梅本さんは、その後も気になって、いとのさんが婦人会の活動から帰ってくるたびに「今日はどうだった?」とたずねたが、母が“一人前”という気持ちを抱いた様子は、最後までなかったという。
「これでお国のためになった」いとこの戦死に感じた“喜び”

家族が誰も出征しておらず、母が「一人前」でないと言われ続けることに、梅本さんも子どもながらに、どこか劣等感を感じていた。
そうした中、太平洋戦争開戦の翌年の1942年、いとこの吉田隆一さん(当時24)が満州(中国東北部)で戦死したとの知らせが届く。親戚から戦死者が出たことに、梅本さんが抱いた感情は、悲しみではなかった。
「戦死したときに私、嬉しかったんです。うちの親戚で戦死者が出た。これでお国のためになったというふうな気持ちになってね。悲しいというより、うれしかったんです、戦死が」
梅本さんは、いとこの吉田さんの遺骨が収められた白い包みが届いたとき、「私のいとこが死んだんや」と、喜びながら周囲の友人に言って回ったという。
吉田さんの葬式は「村葬」として、村をあげて行われた。国のために命を捧げたことを、すべての人が称えていた。悲嘆にくれる空気は、まったくなかったのである。
「本当に申し訳ない」戦後80年経ったいま、抱く“後悔”

梅本さんが11歳だった1945年8月15日。日本は敗戦を迎えた。
社会全体を覆っていた空気は一変した。梅本さんの母・いとのさんを“一人前でない”と言っていた人たちも、「うちは主人も息子も兵隊に取られて帰ってこない。おばちゃんの勝ちやったな」と漏らした。
日本が負けることを想像すらしていなかった梅本さんも、呆然とした。生活は戦時中よりむしろ、戦後の方が苦しくなり、ひどい食糧難にあえいだ時、初めて戦争を恨んだという。
いとこの戦死に「嬉しさ」を覚えたことも、いま思い返すと、強い後悔の念に駆られる。
「ようあんな気持ちになったなと、今から思うとね。いとこに本当に申し訳ない。いとこが亡くなったのをあんなに喜ぶって、(これほど)馬鹿げたことはないんですね」
「せやから、その時は全体がそういう雰囲気やったんやろなと思います。いいとか悪いとかいうのではなしに、そういう世界やったんですね」
市民の間に蔓延した“同調圧力”が、戦争遂行の推進力となったという現実は、現代を生きる私たちにも、鋭く突きつけられている。
取材を終えて
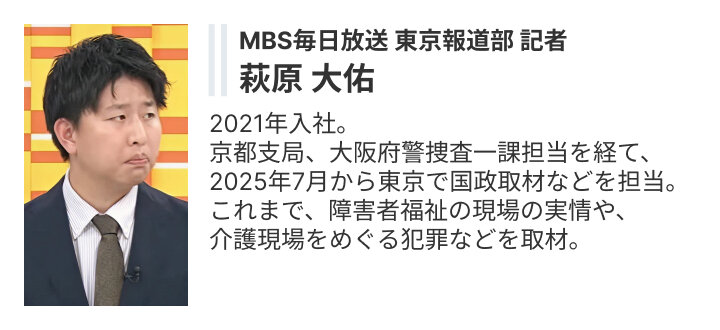
いとこの戦死が「嬉しかった」という言葉に、私はまず驚いた。今の価値観からすれば、自分の親戚の死が「嬉しい」などということは、到底考えられないからだ。ただ、梅本さんが話してくださった当時の社会の雰囲気に目を移すと、果たして自分も同じ状況に置かれたらどう感じていたのかを思わずにはいられない。現代の社会を生きている中で、「おかしい」と感じても、誰かが言っていることに合わせたり、事なかれ主義に走ったりしてしまうことは、誰しも一度は経験したことがあるだろう。こうしたひとつひとつの積み重なりが“同調圧力”を生み出し、社会をある方向へ大きく動かしてしまうのかもしれない。そう考えると、梅本さんが生きた社会、体験した“空気”が、決して他人事とは思えない。
梅本さんが抱いている後悔を繰り返さないためには、こうした当事者の体験談を次の世代に身近な危機として伝えていくことが不可欠だ。そして、“同調圧力”に囚われず、何か感じたときには立ち止まって声を上げ、そのことについて社会全体で考え、話し合うことが大切だろう。こうした思いを持ち続け、取材活動を続けたいと考えている。
※この記事は、JNN/TBSとYahoo!ニュースによる戦後80年プロジェクト「#きおくをつなごう」の共同連携企画です。記事で紹介した「国防婦人会」や「村葬」についての情報に心当たりのある方は「戦後80年 #きおくをつなごう」サイト内の情報募集フォームにご連絡ください。また、企画趣旨に賛同いただける方は、身近な人から聞いた戦争に関わる話や写真を「#きおくをつなごう」をつけてSNSに投稿をお願いいたします。
2025年10月20日(月)現在の情報です