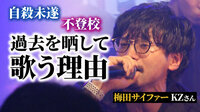2025年11月04日(火)公開
『命がけの出産』赤ちゃんの足型を副葬品に 生と死が身近にあった、縄文人の死生観 土偶や土製品に込めた願い
編集部セレクト

膝を立てて座り、ストレッチするかのように腕を組んだ珍しい姿。1952年に福島市で出土した国の重要文化財「しゃがむ土偶」は、縄文人が“特別な願い”を込めて制作したと考えられています。考古学が専門の京都文化博物館・山崎頼人学芸員は、「縄文人の出産の様子を表している可能性がある」と話します。祈りの象徴、という説もありますが、縄文時代は座って子供を産む、『座産』が行われていたことから、その様子を表現しているとみられています。
縄文時代の出産は“命がけ”で、出産時に命を落とすことも多く、縄文時代の土偶のほとんどは女性で、胸やお腹を強調したものも多く作られています。これは、安産や子孫繁栄を祈願していたと言われています。
衛生状態や食料事情が悪く、医療が発達していない縄文時代では、出産も子育ても大変だったことでしょう。青森市にある世界遺産・三内丸山遺跡では、大人の墓が約470墓見つかったのに対し、子どもの墓が約890墓見つかり、子どもの死亡率が高かったことが推測されています。
函館市で出土した「足型土製品」(複製)。10センチほどの土製品にうっすら刻まれているのは小さな足型です。1歳前後の縄文人のもので、埋葬された人の形見として墓に一緒に埋められたとみられています。「母親の墓に子どもの足型を副葬して、“死後の世界でも一緒にいられるように”という願いがこめられていたのではないか」と学芸員の山崎さんは話します。
死と隣り合わせだった“縄文人の一生”。縄文人は死に対してどんな思いをいだいていたのでしょうか。
宮城県気仙沼市で見つかった「埋葬された縄文人」は、体を折り曲げた姿勢で埋葬されていました。これは「屈葬」といわれ、縄文時代の遺跡で多く確認されています。屈葬には、子宮の中の胎児に見立てて、再生を願うという説や、死者が蘇らないよう願ったという説があります。
学芸員の山崎さんは、「縄文人は、生と死が今よりも身近にあった可能性があるからこそ、命の誕生や成長、自然の再生を願うために土偶などの造形物を作り出して、“まつり”を行い、生命や自然に感謝していたのだろう」と解説します。
縄文時代や土偶についての特別展「世界遺産 縄文」は、京都文化博物館で11月末まで開催されていて、11月1日からは日本に5体しかない国宝土偶のひとつ、北海道函館市の「中空土偶」が展示されています。
2025年11月04日(火)現在の情報です