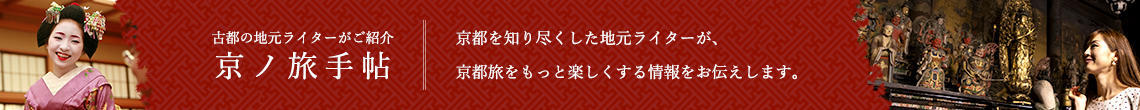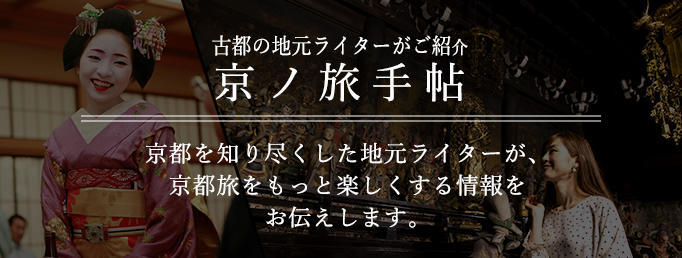忙しい大人にこそ、禅体験
最近なにかと話題のお寺体験。写経ができたり、説法が聞けたり、お坊さんたちの修行の一部を気軽に体験できるということで、外国人観光客にも人気のようです。その中でも、特に支持を集めているのが、禅宗の修行方法の一つである「坐禅」。「忙しくて目まぐるしい毎日...頭を空っぽにする時間なんてない!」そんな大人たちに、ぴったりの体験なのだとか。でも、京都の夏。昼間はとっても暑くて、何もする気が起きない...。今回は、そんな方にもおすすめしたい、涼しい朝夕に坐禅体験のできる京都の2つの寺院を訪れてみました。
そもそも坐禅ってなに!?

坐禅は仏教・禅宗の修行方法の一つ。坐って行う禅、ということで「坐禅」と呼ばれます。インドが発祥ですが、鎌倉時代に中国から伝わってきました。お釈迦さまも坐禅の修行によって悟りを開いたそう!宗派によって、少しずつ方法が違います。
仕事帰り、夜に坐禅を組める「大慈院」へ




初めての坐禅体験、ひとりで行くのは少し緊張する...。そんな時に見つけたのが、大徳寺の塔頭寺院の大慈院。天正13年(1585)創建の歴史あるお寺です。こちらでは、18時から「夜空の坐禅」という坐禅会を開催していて、夜に坐禅が組めます。仕事終わり、職場の仲間と一緒に行く...なんていうシチュエーションが思い浮かびますね。
ご住職の笑顔に迎えられる

桃山時代の装飾が施された門をくぐって、お寺の中へ。坐禅の指導をしてくださるのは、住職の戸田惺山(とだせいざん)さんです。ちょっと不安だった初坐禅、優しい笑顔で出迎えてくださり、なんとも言えない安心感で満たされました。
さっそく、組んでみる



簡単な説明を受けたところで、一度坐禅を組んでみることに。坐禅独特の座り方、結跏趺坐(けっかふざ)・半跏趺坐(はんかふざ)もありますが、初心者にはなかなか難しく、私たちも苦戦...。「大切なのは、楽で安定していることです。脚の組み方じゃないんですよ~」と、戸田さん。「難しいことはポイっとして、心を無にすることがなにより大事」なのだそうです。手は「法界定印(ほっかいじょういん)」と呼ばれる形。右手と左手の親指で円を作り、おへその下くらいの位置に置きましょう。一番自分が集中できる姿勢で、お釈迦様のように目線を落として、肩の力を抜いて、ゆっくりと呼吸をします。
警策を受けて、気持ちも新たに




集中が切れそうになったり、眠たくなったときには警策(けいさく、きょうさく)を受けましょう。背中をパシッと叩いてもらうと、気持ちも新たに集中できますよ。警策を受けたいときは、合掌が合図になります。警策を受ける時は、両手を身体に巻き付ける体勢で、後には御礼の合掌も忘れずに。
頭が空になっていく




この「夜空の坐禅」は、夜の静けさを感じつつ、一日の終わりに気持ちを安らげる時間を作ってほしいという戸田さんの思いで開催されています。情報があふれる世界で、自分自身から自由になる時間、お寺の清廉な雰囲気の中で、みんなで坐禅に向かう時間。心地の良い静けさがあたりを包み、次第に頭の中が空っぽになっていきます。
気持ちを共有する

一度目の坐禅は約15分ほどで終了。しばし休憩です。苔や松が美しい庭を眺めながら縁側で坐禅を組めるなんて、今さらながら本当に感激!ほっ...と一息つきながら、みんなで気持ちを共有し合う時間も、素敵です。
「戸田さん体操」で身体をほぐす!


大慈院の坐禅体験の特徴の一つが、住職の戸田さん考案の「戸田さん体操」!先ほどまでのしっとり落ち着いた気持ちを一旦忘れて、みんなでワイワイ体を動かします。畳に寝転がって、普段はしないような体勢で筋肉をゆっくり伸ばしていると、段々と身体がほぐれてきて軽くなっていくのを感じます。畳の部屋に上がるということ、ましてやゴロゴロできる機会なんてめったにない今日この頃...フローリングよりもソフトな畳の感触がとても心地よかったです。
二度目の坐禅に臨む



身体をほぐした後は、二度目の坐禅です。夕暮れから夜へと時間が移る中、ろうそくの火が揺れて、なんとも幻想的。鈴が鳴ると、坐禅の始まりです。一度目の坐禅よりも、身体が軽く、心も軽い気がする...。「戸田さん体操」のおかげでしょうか。周りの音も、だんだんと遠くなっていきます。戸田さんや友人たちの息遣いが聞こえるほどの静けさ。しばらくすると、戸田さんの読経の声が聞こえてきます。音が全くないのも良いけれど、シーンとした夜に響くお経に、より集中力が増すような気がしました。
すべてを終えて、語らう

二度の坐禅を終えたら、体験プログラムは終了。お茶とお菓子をいただきながら、戸田さんと参加者でさまざまなことを語り合う時間です。きょうの感想や、普段感じていること、疑問、悩み。普段生活していて、みんなで何の気兼ねもなく話せる時間なんて案外少ないのかも...。温かな空気感にずっと浸っていたいくらい、素敵な時間でした。体験前よりも、確実にいろいろな部分が軽い!明日からも、また頑張れそうな気がします。

■ 大徳寺 大慈院
京都市北区紫野大徳寺町4-1
075-492-2958
■坐禅体験データ
開催日...毎月一回水曜日
時 間...18時30分~20時30分
料 金...2000円
※お問い合わせは、株式会社のぞみ(075-351-9915)まで
一乗寺にある禅宗の寺「圓光寺」
夜の坐禅、とっても心地よかった...。次は朝の涼しい時間帯を有効活用したいと、いつもより早起きをして、朝の坐禅にひとりで挑戦してみることに。慶長6年(1601)に徳川家康が開いたとされる学問所がルーツの圓光寺さんへ。こちらでは、坐禅から、掃除を通して自らを見つめ直す作務(さむ)、仏教や禅についてわかりやすく教えてくれる法話、禅宗の朝食である粥坐(しゅくざ)までを体験することができます。京都の中心部から少し離れた一乗寺というエリアにあり、あたりはとても静か。街の喧騒を忘れて、なんだか遠くまで来たような気分です。
見事な枯山水庭園に迎えられる
門をくぐり、坐禅道場までの道の途中には枯山水庭園「奔龍庭(ほんりゅうてい)」が。枯山水庭園にはシンプルな造りのものが多いのですが、どこか華やかさや迫力を感じます。白砂は雲海を、石組は龍を、そびえる石柱は稲妻を表しているのだとか。庭の中を通る道と庭の間には仕切りがなく、庭の造りを間近に見ることができます。
午前6時、修行開始

修行の開始は6時、まずは坐禅から。初心者さんは15分前に集合し、坐禅の座り方や呼吸の方法などを教わりましょう。朝の澄んだ空気の中に、鈴の音が響きます。近年まで尼僧たちが修行していたという禅堂は、凛として神秘的な雰囲気。20分間の坐禅を二度、行いました。
作務、法話


坐禅を終えた後は、作務と呼ばれる修行。歴史ある美しい庭や建物を掃除をしながら、自分の中にある悪いものや雑念を排除していきます。住職自ら話してくださる法話では、仏法や禅について、知ることができます。大人になって新しく何かを学ぶ機会ってなかなかないですよね。なんだか新鮮な気分でした。
最後の修行、粥坐

そろそろお腹が空いた...と思っていた頃に、最後の修行。粥坐の時間です。粥坐とは、禅宗における朝食のこと。他の参加者や住職と一緒に、粥と漬物というシンプルな朝食をいただきます。朝から活動していたからか、いつもより質素な朝食なのにとてもおいしく感じました。
修行を終えた後は、境内を散策

近世に造られた十牛之庭(じゅうぎゅうのにわ)を眺めながらまったり。気持ちがとても落ち着いてきて、心がとても穏やかになります。周りの風景に自分が溶け込んでいくような、不思議な感覚です。水音がかすかに響く水琴窟や、手入れされた竹林など、素晴らしい境内はいつまでも見ていられそう...。
お寺を後に
少し長居をしてしまいましたが、そろそろ帰らないと。このすっきりとした状態なら、何でもできる気がします。ちょっと遠出をしてみるのもいいし、ずっと行ってみたかったカフェを訪ねるのもいいな...と考えにふけります。朝から坐禅体験をしたおかげで、こんなに一日が楽しみになるなんて!朝一の体験なので、仕事や観光の前にもおすすめですよ。
■ 圓光寺
京都市左京区一乗寺小谷町13
市バス「一乗寺下り松町」下車徒歩約10分、叡山電車「一乗寺」下車徒歩15分
075-781-8025
■坐禅体験データ
開催日...毎週日曜日
※前日までに電話での予約必須
時 間...6~8時
料 金...1000円(拝観料込)
もっと知りたくなった、禅の世界

今回は夕方と早朝、2つの坐禅を体験してみました。余計なことを考えず、ただ座って集中する時間。心も身体もすっきりクリアになって、頭の中が整理され、学校の授業や講義では何となく知っていた「禅」について、もっと深く勉強してみたくなりました。皆さんも、涼しく心地よい夏の朝夕に、自分を見つめる時間を設けてみませんか。
禅体験、おすすめの3寺院
京都市内でも禅体験のできるお寺はたくさんありますが、その中でも3つのおすすめ寺院をご紹介。
庭を眺めながら坐禅が組める「両足院」

祇園にある禅宗の寺・建仁寺の塔頭寺院。室町時代中期まで、禅僧によって書かれた漢詩「五山文学」の最高峰の寺院とされていました。境内は通常非公開ですが、坐禅体験時は中に入ることができます。初夏には半夏生が美しく色づく庭が特別公開され、寺宝や茶室も見ることができます。
■ 両足院
京都市東山区大和大路通四条下る4丁目小松町591
市バス停四条京阪から徒歩5分
075-561-3216
体験できるもの:坐禅

坐禅以外にも多彩な禅体験がある「勝林寺」
毘沙門天を本尊とする寺院で、天文19年(1550)に創建された東福寺の塔頭寺院。坐禅や写経・写仏、朝粥、ヨガなど、さまざまな体験ができるので、幅広い年代から人気を集めています。毎日何かしらの体験を実施しており、スケジュールを合わせやすいのも魅力的!季節や時期ごとにいただける御朱印も話題のようです。
■ 勝林寺
京都市東山区本町15-795
市バス停東福寺から徒歩5分
075-561-4311
体験できるもの:坐禅、写経・写仏、坐禅とヨガ、坐禅と朝粥
禅体験は休日を中心に開催「大仙院」
永正6年(1509)創建の大徳寺塔頭寺院。床の間や玄関は現存する日本最古のものとして、国宝に指定されています。あの千利休ともゆかりがあるのだとか!見どころは方丈を囲む3つの枯山水庭園で、国の特別名勝にも指定されています。坐禅体験は土日を中心に実施されているので、旅行で京都に来た場合も参加しやすいですよ。
■ 大仙院
京都市北区紫野大徳寺町54-1
市バス停大徳寺前から徒歩8分
075-491-8346
体験できるもの:坐禅(3~11月は17~18時、12~2月は16時30分~17時30分)
※土日以外に毎月24日には報恩坐禅もあり