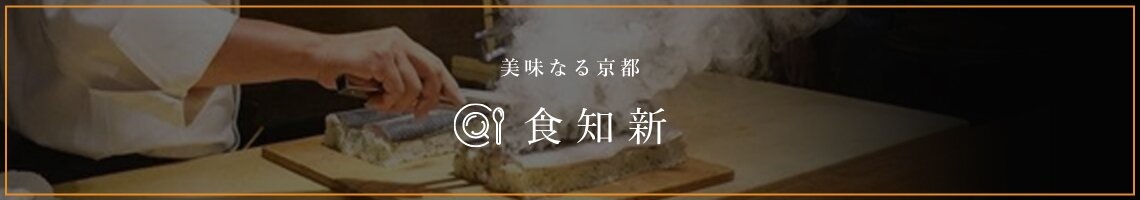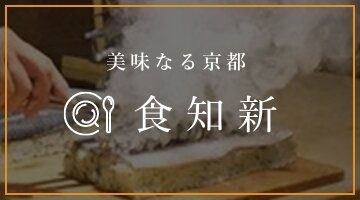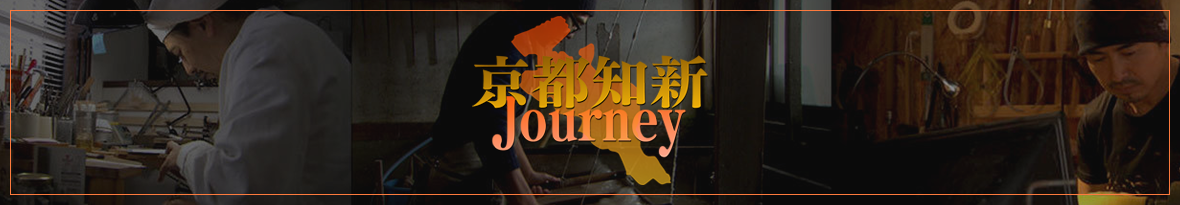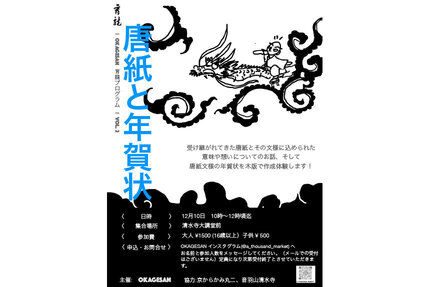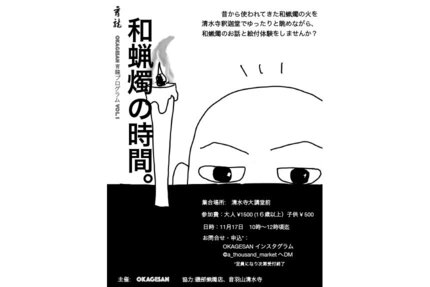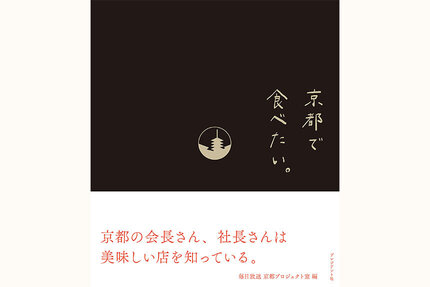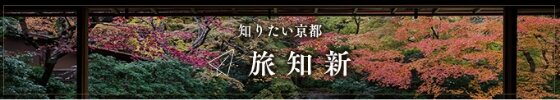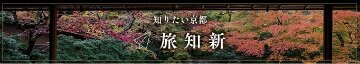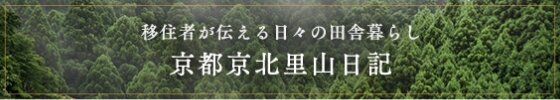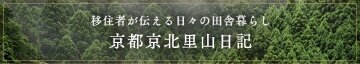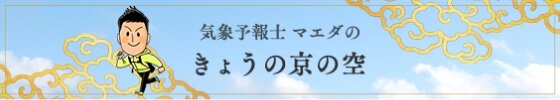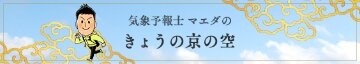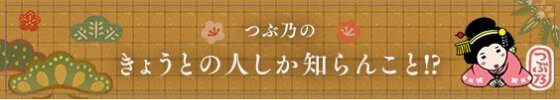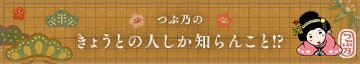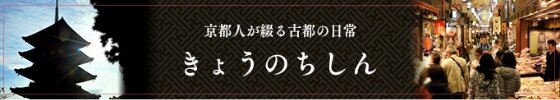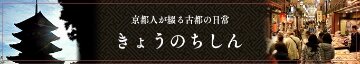「京都知新」は、1200年に渡り受け継がれてきた京都文化の「動」=「新」の部分に光をあて、
「京都を温(たず)ねて新しきを知る」番組です。
京都で活躍する、アーティスト、職人、伝統芸能伝承者、料理人などへの取材を通して、
現在進行形の「京都」を浮き彫りにします。
毎週日曜 あさ6時15分~6時30分OA
(関西ローカル)
NEXT PROGRAM
次回予告

2026年02月22日(日)放送
#493 ひがしやま 司
宮下司
土壁と白木のカウンターが印象的な、東山三条の割烹「ひがしやま 司」。
お料理は、底冷えのする季節に身体を温める、「すっぽんと聖護院大根」を使った先付に始まり、寿司めしを昆布だしで煮込んだオリジナル料理「しゃりがゆ」。旬のホワイトアスパラガスを皮で包んだ「生春巻き」など、訪れる人をあっと驚かせるような創意を巡らせた品々が並びます。
そんな料理を考案するのが、「ひがしやま 司」 主人 宮下司さんです。
京都の名店「祇園 丸山」や「祇園 さゝ木」で16年にわたり研鑽を積み、2021年に独立しました。
大切にしているのは、日本料理の伝統的な構成や食材そのものを生かすという精神です。その上で、他にはない組み合わせを考案し、食材の持ち味を損なわない絶妙な塩梅で表現することこそが、自身の和食への敬意だと考えています。
最近では、去年入った弟子の石岡拓さんの存在が、料理にさらなる深みを与えています。
ふたりが息を合わせて生み出す新たな和食の形が、訪れるお客さんを魅了してやみません。
何より「食べる人の心地よさ」を第一に考え、その月に味わってほしい食材を、遊びすぎず、かつ驚きのある仕立てで提案したい。
京料理の技を礎に、型にとらわれない豊かな味わいを、宮下さんは今日も追求し続けています。
【INFORMATION】
●ひがしやま 司
〒605-0036
京都府京都市東山区西町127番地 三条白川橋ビル 2F
TEL:075-771-4696
Instagram:https://www.instagram.com/higashiyama.tsukasa/
●K by Lexus Amagasaki
Instagram:https://www.instagram.com/imuraartgallery/
お料理は、底冷えのする季節に身体を温める、「すっぽんと聖護院大根」を使った先付に始まり、寿司めしを昆布だしで煮込んだオリジナル料理「しゃりがゆ」。旬のホワイトアスパラガスを皮で包んだ「生春巻き」など、訪れる人をあっと驚かせるような創意を巡らせた品々が並びます。
そんな料理を考案するのが、「ひがしやま 司」 主人 宮下司さんです。
京都の名店「祇園 丸山」や「祇園 さゝ木」で16年にわたり研鑽を積み、2021年に独立しました。
大切にしているのは、日本料理の伝統的な構成や食材そのものを生かすという精神です。その上で、他にはない組み合わせを考案し、食材の持ち味を損なわない絶妙な塩梅で表現することこそが、自身の和食への敬意だと考えています。
最近では、去年入った弟子の石岡拓さんの存在が、料理にさらなる深みを与えています。
ふたりが息を合わせて生み出す新たな和食の形が、訪れるお客さんを魅了してやみません。
何より「食べる人の心地よさ」を第一に考え、その月に味わってほしい食材を、遊びすぎず、かつ驚きのある仕立てで提案したい。
京料理の技を礎に、型にとらわれない豊かな味わいを、宮下さんは今日も追求し続けています。
【INFORMATION】
●ひがしやま 司
〒605-0036
京都府京都市東山区西町127番地 三条白川橋ビル 2F
TEL:075-771-4696
Instagram:https://www.instagram.com/higashiyama.tsukasa/
●K by Lexus Amagasaki
Instagram:https://www.instagram.com/imuraartgallery/





 京都知新公式X
京都知新公式X 京都知新公式Facebook
京都知新公式Facebook 京都知新公式Instagram
京都知新公式Instagram