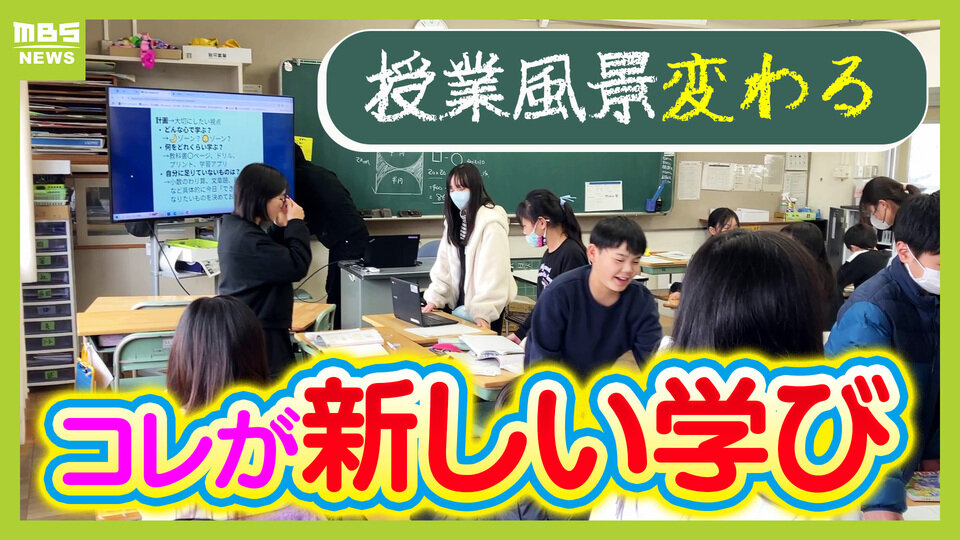「では、みなさんに時間を委ねます。30分!」担任の声をきっかけに、算数の授業風景が一変した。机を運んで移動を始める児童、すぐに複数のグループ席ができた。その輪に入らない児童もいる。声を出して図形の課題を解くにぎやかな男児ペア。その横で図形問題には目もくれず、計算問題を解く女児。児童たちは、教室を前へ後ろへと歩き回り、自由に会話もしている。
でもこれは学級崩壊ではない。「自由進度学習」という新しい学びの姿だという。
変化が激しく予測困難な社会、多様な価値観…昔のモデルが通用しにくい時代に『新しい学びが必要だ』とあちこちで指摘されているが、学校現場でどんな学びが実践されているのか、目にする機会は少ない。最先端の取り組みと課題を取材した。
◆自由進度学習で目を見張る成績向上

奈良県生駒市の生駒南小学校。ことし創立150年を迎える伝統校は、児童への懇切丁寧な教育が特徴だというが、近年、大久保智子校長は「言われたことだけするのではなく、中学生になり私たちの手を離れて自ら考えて取り組める主体性が必要、そのため何かをしないと。」と課題を感じていた。
3年前にふとしたきっかけで自由進度学習を知り、5年生で試行したところ、翌年の小学6年生全国学力テストで目を見張る成績向上がみられた。児童アンケートでも「あの勉強方法をもう一度やってみたい」という声が届き、今年度は全学年を対象に本格実施に踏み切った。
◆“自由の幅”は学年によって違う
自由進度学習は、集団講義型の授業と違って、子どもたち自らが計画を立てそれぞれのペースに合わせて自主的に学んでいく。「わかったことが嬉しい」「もうすこしやりたい」「友達に聞ける、友達に教えられる」といったプラス面が期待できるという。
6歳から12歳まで年齢差がある小学校だけに、裁量には幅をもたせている。低学年は、「問題を解く順序を自分で決める」など限定的な自由で、高学年になれば、授業時間のほとんどを児童に委ねる、という感じだ。
科目も、算数は取り入れやすく、国語は難しいなど、運用にコツがいるようだが、6年生の算数の授業ではこんなシーンが見られた。
◆一人で黙々と学ぶ児童「どうして一人でやっているの?」と聞く

「線対称と点対称って、何が違うん?」(児童)
「線対称は折って同じになるやつ、点対称はひっくり返して同じになるやつ」(別の児童)
「わかった。ありがとう」(児童)
別の席では全く算数の教科書を解かずに、タブレットに何かを入力している女児がいる。何をしているの?と聞くと、「(教科書が)全部終わったんで、みんなのために、算数の問題を作ってるんです」との答え。

別の、ひとりで黙々と学ぶ児童に、どうして一人でやっているのか、と聞くと。
「問題が分からない日は、友達に聞きたいので一緒にやる。問題が分かる日は集中したいので一人でやる」との返答。
なるほど、それぞれ考えたうえで、自身の行動を決めている。
◆自習とは 似ているようで…何が違う

「自習みたいでいい。」と、概ね好評な児童らの感想。ふと疑問が湧く、自習とは何が違うのだろう?
「自習を、“プリントなど課題を渡されて自分のペースで取り組むこと”と見ると、自由進度学習との違いは、“自己選択と自己決定”ではないでしょうか」と担任が解説する。
児童には、「苦手をきちんと分析することが学びのスタートだ、と教えて、苦手を見つけたら『じゃあ、どうする?』と課題克服を考えて取り組ませる」という。そのやり方が「35人いたら35通り。結果バラバラな学び方」になるというのだ。
ある児童が、「ふわふわとして集中が切れたので、5分休憩!と選択しても、それが自身を分析した結果であるなら、じゅうぶん評価ポイントになる」という。
保護者からは、「自分で学ぶ力は中学校に向けて必要。」「家で勉強を教えてほしいと言ってきて驚いた。」「良さはわかるが、うちの子には合っていないと感じる。」など様々な声が届いているという。
解き方ではなく、学ばせ方そのものを教える授業風景。中には、「先生は何を教えているんですか?」と聞く親の声もあるとか。
◆「個別最適な学び」は国の方針

ひとりひとりに合わせた学習は、国の方針になりつつある。【令和の日本型学校教育の構築を目指して】と題した2021年の中央教育審議会の答申で、「個別最適な学び」が明記され、「協働的な学び」との一体的な充実が求められた。
かたちが示されて3年。長野県や広島県、石川県加賀市や名古屋市、芦屋市などで方向性が示されているそうだが、個別最適な学習法が全国各地で一般化された、とは言い難い状況だそう。奈良県生駒市も今年度策定した第3次教育大綱に「自分で選び、自分のペースで学ぶ」と掲げているが、12ある小学校のうち、取り組みには濃淡があるそうだ。
学校現場の負担は増しそうだ。授業前の準備も増えるし、児童にあわせたアドバイスも必要。“自由な子ども”への目配りも要る。授業が「ただのおしゃべりになってしまう」リスクもある。生駒市教委によると、教員側に新しいスキルが求められることも、温度差の一因ではないかという。
◆「実施が難しいと感じる先生も多くいます」

生駒市内の小学校で教える別の教員は、「取り組む先生は増えたように思います。しかし、どのように進めていくのか、どの単元で取り組みやすいのかわからず、実施が難しいと感じる先生も多くいます。」と実情を明かす。
この教員は、「理念と現実のギャップを埋めるためには教員向け研修や、それを通した共通理解、職員間の情報共有など、ある程度の期間が必要ではないでしょうか。」と指摘。さらに、「日々の業務などあるなかで、多くの研修を負担に思う先生方は多いと思います。」とも指摘している。
◆ポイントは「授業の中で、子どもが主人公になる」

総合型選抜等で大学に進学する人が増えているように、いまは学力だけを見る時代ではなく、本人が決めた“学びの軸”や、その意欲も評価する時代だ。
生駒南小学校では、「授業の中で、子ども達が主人公になる場面を意図的に増やしている」という。
今後、子どもたちが出会うであろう別々の課題や壁。それぞれが主人公として乗り越える力を育てたい。そういう共通した目的を理解し、どのような手段で実践していくか。学校現場では、目の前の状況に合わせながら模索が続いている。
小野智也(MBS報道情報局 デジタル担当)