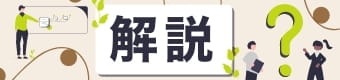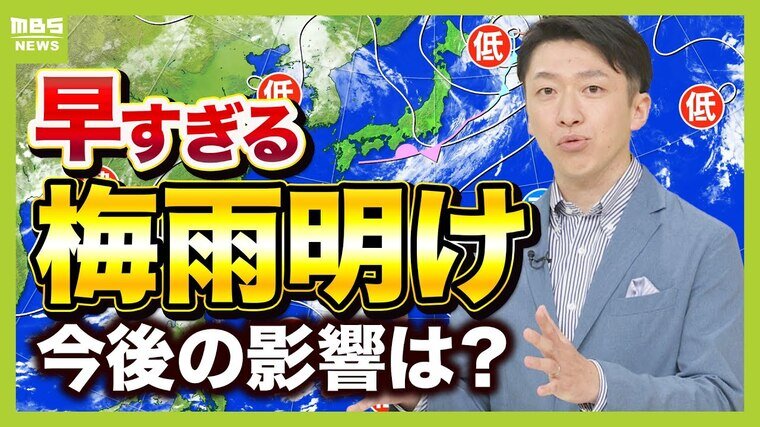梅雨明けした奈良公園を訪ねました。外国人観光客の女性は「暑すぎる!涼むのにアイスクリームが手放せないわ」と驚き、鹿が水分補給をしながら木陰で休む姿が見られました。
6月27日に梅雨明けしたとみられる、との発表。平年より22日早く、1951年の統計開始以降、過去最早となります。梅雨入りしたのは今月9日でしたから、期間はわずか18日間で2番目に短く、通常の梅雨期間が約40日程度であることを考えると、半分にも届かない短さです。
全国6か所で37℃を超える 福知山市が全国最高の37.5℃
梅雨が明けるとあっという間に暑い日が続きます。6月30日(午後2時半)の段階で、全国で気温の高い順に以下のようになっています。
1位 福知山(京都府 37.5℃)
2位 和田山(兵庫県 37.3℃)
3位 多治見(岐阜県 37.1℃)
3位 熊谷(埼玉県 37.1℃)
3位 前橋(群馬県 37.1℃)
6位 伊勢崎(群馬県 37.0℃)
7位 古河(茨城県 36.9℃)
7位 久喜(埼玉県 36.9℃)
9位 萩原(岐阜県 36.8 ℃)
9位 揖斐川(岐阜県 36.8℃)
9位 佐野(栃木県 36.8℃)
なぜこんなに梅雨明けが早かったのか
前田智宏気象予報士によると、早い梅雨明けとなった主な要因は、太平洋高気圧の勢力が強まったことにあります。この先も太平洋高気圧の勢力が強まり、気象の主役になっていくという見通しになったため、梅雨明け(とみられる)の発表に至りました。太平洋高気圧が強くなる理由は複数あるといい、前田予報士によると、偏西風が平年よりも北を吹いていることにくわえ、「南の海上で低気圧が発生し、いわゆる台風予備軍となっている。この低気圧が太平洋高気圧を強める働きがある」ということです。
「低気圧が上昇気流をもっているのに対して、太平洋高気圧は下降気流を持っています。低気圧側でのぼった熱い空気が高気圧を押し込むような形で、高気圧のパワーがどんどん強まってしまうのです。このあとは台風発生も心配になってきます」(前田智宏予報士)
早すぎる梅雨明けによる水不足と農作物への影響
今年の梅雨はメリハリが大きく、「降る時はざっと降って、すぐ上がって晴れて、晴れたらカンカン照り」という状況が続いていました。早い梅雨明けで水不足が懸念されるところですが、実際に雨量は足りているのでしょうか。各地域の梅雨期間中の雨量を平年比で示しました。
地域によって雨量には大きな差が出ました。短い梅雨でしたが大阪や和歌山は6月に度々大雨となったため、梅雨期間全体の8〜9割の雨が降りました。しかし、北部の豊岡では41%、徳島では37%、潮岬にいたっては19%とかなり少ない状況です。
「地域差自体は毎年あるものですが、特に太平洋側は基本的に気候的に雨の多い地域です。そういった地域で雨量が少なくなってしまうと、特産のみかんや、米など農作物への影響が心配されます」と話します。
『心配なのは水不足によるコメへの影響』
農作物への具体的な影響について、米と農作物の産地に詳しい宇都宮大学の松平尚也助教にお話を伺いました。松平さんによりますと、「最も心配なのは水不足によるお米への影響です(現在のコメ不足は、2023年の猛暑の影響とも)。また、高温が続けば、農作物全般も影響を受けて、価格高騰につながる可能性もある」ということです。
お米は5月から7月にかけての雨量が非常に重要だそうで、本来なら雨が多い7月に降らないとなると、影響が懸念されますね。現時点では今年のお米の生産量は平年より多くなる見込みですが、水不足が続けば心配です。
当面は『暑さ』への警戒が必要です
梅雨明け後は厳しい暑さに警戒が必要です。7月以降の週間予報は晴れや雲が続き、京都は厳しい暑さとが予想されて、35℃、36℃、37℃などと連日の猛暑が予想されます。また夜間の気温も下がらず、大阪の最低気温は25℃を下回る日がほとんどなく、寝苦しい熱帯夜が続く見込みです。
湿度についても注意が必要です。「太平洋高気圧は湿気たっぷり含んでいます。それに覆われるということは、どんどんムシムシした体にこたえる蒸し暑さになっていくでしょう」と前田予報士は説明します。
さらに、気象庁の3か月予報によれば、7月も8月も9月も平年よりも気温が高くなる見通しです。「いつもの夏よりも気温が高い。つまり言い換えると7月は猛暑、8月も猛暑、9月は猛烈残暑ということになります」「6月に真夏がやってきた、と意識していただき、9月まで暑さとの長いお付き合いになってしまいそうです」と前田予報士は締めくくりました。
外での活動や、仕事をされる方は特に、熱中症対策をしっかり行い、身の安全を確保することが重要です。