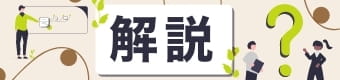今夏の参院選を前に活発化する「消費税減税」の議論。各党の案は家計へどう影響するのでしょうか? 消費税率を引き下げることによるメリット・デメリットは? 第一生命経済研究所・首席エコノミスト永濱利廣氏と、野村総合研究所エグゼクティブ・エコノミスト木内登英氏の見解をもとにまとめました。
各党の減税案をおさらい 税収はどれくらい減る?

消費税減税について、まず自民党では党内で意見がわかれています。今夏に選挙を迎える参議院議員は「食料品に限り2年間0%」を主張していますが、一方で石破総理は減税に否定的。
同じ与党の公明党は、「食料品の5%減税」を主張しています。立憲民主党は「原則1年間食料品を0%」、日本維新の会は「2年間食料品を0%」にする案。国民民主党・共産党・れいわ新選組は「消費税全体を一律5%」とする案を示しています。

財務省の試算では、食料品の軽減税率8%が0%になると、税金は年間5兆円の減収となります。消費税全体(10%・8%)を一律5%に下げると、年間15兆円の減収となる見通しだということです。
さらに第一生命経済研究所・永濱利廣氏が詳しく試算すると、軽減税率を8%から7%に下げると年間6000億円の減収、消費税全体を1ポイント下げる(10%→9%・8%→7%)と、年間2.4兆円の減収になるということです。
消費税の「逆進性」って?

そもそも減税を求める声が上がっているのは、食料品などの物価が上がっていることがきっかけです。しかし、議論の上で抑えておきたいポイントが、消費税の「逆進性」です。
基本的に税金は高所得者ほど高負担ですが、消費税は年収400万円世帯でも800万円世帯でも負担が変わりません。消費税の負担が仮にどちらも8万円だった場合、収入に占める割合は400万円世帯で50分の1。800万円世帯で100分の1となります。つまり所得が低い人ほど負担が重くなり、税金の基本の考え方とは逆になる、ということが一つの問題となっているのです。
専門家でも割れる見解

改めて、消費税減税案について見てみます。「消費税一律5%」案や「食料品の消費税0%」案がありますが、物価高で困っている低所得者の支援という側面では、食料品を0%にするほうが効果的という考え方も。一方で、一律5%に下げれば景気アップに寄与するかもしれないほか、全員に恩恵があるという考え方もあります。
消費税を「一律5%」にする案は、15兆円の税収減につながるほか、高収入の人にも恩恵が出るなどの観点から、第一生命経済研究所の永濱利廣氏、野村総合研究所の木内登英氏のどちらも「難しい」という見解を示しています。
一方で、「食料品0%」案については両者で見解が割れました。軽減税率を0%にするとGDPを1年間0.43%押し上げる(野村総合研究所の試算)ということで、永濱氏は「現金給付の倍の効果を得られる」とみています。一方で木内氏は、「5兆円の税収減につながることを考えれば、費用対効果に疑問がある」という見方を示しています。
そのうえで、「期間限定」の減税には両者とも疑問を呈しています。永濱氏は、日本の軽減税率はG7の中で最も高いほか、エンゲル係数(支出に占める食料費の割合)は、G7の多くが十数%であるのに対し、日本は28%であることから、減税を恒久的に行うべきだと指摘。
木内氏は、消費税は“一度下げたら戻せない”ため、「結果的には恒久的な措置になってしまう」という見解です。
財源はどうする?
消費税を減税した場合の、代わりの財源はどうするのか。よく挙げられるのが、「法人税」を財源にすることはできないのかという案です。永濱氏は、法人税を引き上げる代わりに投資減税を行うことで可能だといいます。
対する木内氏は、法人税を財源にすべきではないと指摘。法人税は景気に左右され不安定なうえ、法人税が安いほうが海外からの投資を呼び込める、逆に言えば法人税が上がると企業の海外競争力が低下するなどと分析しています。
各政党が示している財源案は以下の通りです。

自民党:赤字国債
公明党:財源検討中 赤字国債はダメ
立憲民主党:政府の基金を取り崩し 特別会計の剰余金を活用
日本維新の会:定額減税をやめた税収増分など
国民民主党:経済成長 赤字国債など
共産党:法人税増 富裕層課税
れいわ新選組:赤字国債
赤字国債に頼ってもいいの?

多くの党が提案している赤字国債は、消費税減税の財源にするべきか否か。
日本の“財布”を見ると、入ってくるお金「歳入」の約3分の1は公債金(借金)です。使うお金「歳出」は、約4分の1が国債費(過去の借金の返済と利息)です。こうした状況が続くなか、赤字国債は年々増えていき、2024年度末の普通国債残高は1105兆円(財務省より)と、G7の中で最も高くなっています。こうした状況でも赤字国債をさらに増やし“目の前の苦しい状態”を抜けるのか、これ以上“借金”してはいけないのか…。

木内氏は赤字国債に頼るべきではないという考えです。今は大丈夫だが、いつか日本国債の信用は落ちる可能性があるほか、次世代が使えるはずだったお金が減るため、将来の成長を阻んでしまうと指摘しています。

永濱氏さんは「まだ(少しは)大丈夫」という見解です。国の税収は4年連続で増えて過去最高で、“政府は稼ぎすぎているため国民にかえすべきだ”としたうえで、赤字国債が多いとはいえ、日本の国債信用度はドイツに次いで2番目に高いというデータもあると指摘します。
消費税や物価高対策のあり方は?

では結局、消費税の税率の変更も含め、物価高に対してどんな政策を打ち出すのがベストなのでしょうか?
木内氏は、低所得者に絞って、回数を制限して直接現金を給付するべきだといい、財政赤字は増やすべきではないという見解を示しています。
永濱氏は恒久的に軽減税率を下げるべきだという見解。給付の場合、対象者をどこで線引きするのかという問題が生じると指摘します。区切りやすいのは住民税非課税世帯ですが、実はその7割は高齢者で、中には金融資産を持つ人もいると指摘しています。
物価高対策や消費税をめぐる議論は、参院選に向けて今後も一層熱を帯びていきそうです。
将来的にはこうしたことも覚悟したうえで、今後の選挙を考える必要があるかもしれません。