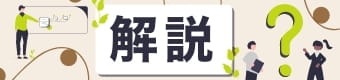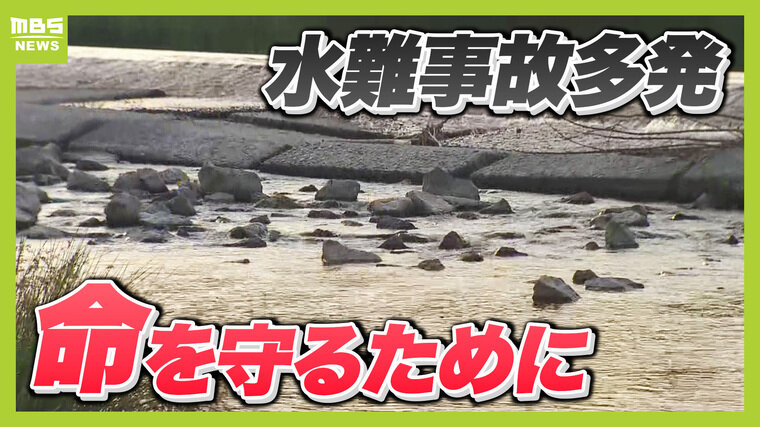いよいよ夏休みのシーズンに入りますが、今年も「水の事故」が各地で相次いでいます。川や海などで命を落とさないために、どんな意識や行動が求められるのか? 長岡技術科学大学教授で、一般社団法人水難学会理事の斎藤秀俊さんに聞きました。(聞き手:松本陸)
水深は「ひざより上は注意信号。腰より上は赤信号」
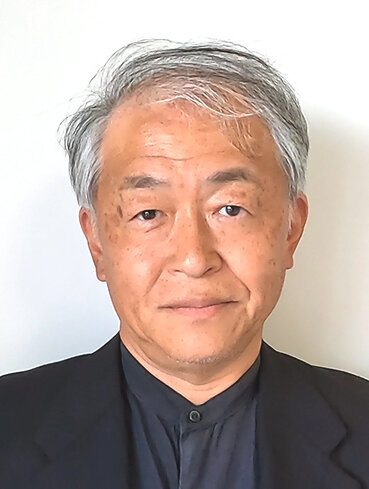
Q 子どもの水難事故、これはやはり親が目を離した間に起きるケースが多いのでしょうか?
「いえ、我々は『放課後水難』と言っていますが、放課後に起きる水難事故、だから平日が多いですよね。学校でいろいろ話をして、『今日の放課後にどこ行く?』という話になった時に、川や海が選択肢としてやっぱり出てくるわけです。そこで事故になってしまうということですよね」
Q 子どもが川遊びなどをする際に、安全な水深はどれくらいと考えればいいのでしょうか?
「ひざ下ぐらいまでの水深で遊んでいれば、基本的には事故に遭わなくて済むということになります。川でも海でも、溺れる原因が何かと言うと、要するに“足のつかない所に、はまってしまった”ということなんです。自由が奪われるような水深、そういう場所には絶対に入り込まないというのが第一の鉄則です」
Q ひざより上ぐらいの深さだと、かなり危険と考えた方がいいでしょうか?
「そういうことです。『ひざよりも上なら注意信号。腰よりも上なら赤信号』と覚えておいてもらうといいと思います」
飛び石など河川構造物の下流側は「思ったよりも深い」

今年6月には兵庫県姫路市の夢前川で、飛び石を渡って遊んでいた男子中学生が川に転落。警察や消防が捜索したところ、飛び石のすぐ近くの水中(深さ2m以上とみられる)で男子中学生が見つかり、搬送先の病院で死亡が確認されるという痛ましい事故が起きました。
Q 中学生が飛び石を渡っている時に川に転落し死亡するという事故が起きました。やはり河川構造物の近くは危険だと認識したほうがいいのでしょうか?
「一言で言うと深くなっているんです。河川構造物のちょっと下流側というのは『洗掘(せんくつ)』という現象が起き、思ったよりも川底が深くえぐられているんですね。そこが事故のポイントになります。
上流側の水深が比較的浅い構造物のところで遊んでいて、偶然下流側に足を踏み入れたり、すべって落ちてしまったりして、構造物のすぐ下流の深みにはまってしまうという事故が散見されますね。今年は結構それが多いと思いますね。
水深が急に深くなっていることが、子どもも大人もすぐに判断できないんですね。せいぜい腰ぐらいの高さだろうと思って入ったら、思いのほか深くて、体全部が浸かってしまって、そのまま浮かんでこないという事故が構造物の近くではよく起きます」
「声を出して飛び込む」のは非常に危険!肺の空気が抜けて浮き上がれない…

飛び込んで遊んでいる際の水難事故も、今年も各地で起きています。斎藤さんは特に「声を出して飛びこむ」行為は非常に危険だと話します。
「大抵はみんな息を止めて飛び込むので、飛び込んだ後にすぐ浮かんできます。ところがだんだん慣れてきて、『よし行くぞ』とか、『ワーッ』とか『キャーッ』とか言いながら飛び込むと、肺の中の空気が抜けちゃうんですよね。
肺の中の空気は、ある意味“浮き具”なので、その空気が抜けた状態で水の中に沈むと、一気に水底の方までどんどん沈んでいくと。そうすると、『あれ?なんか今回だいぶ深く潜ったな』と思って、水面の方に一生懸命手をかいて足をかいて浮かぼうとするんですが、その間に我慢できなくて、水中で息をしようとして水を飲んで、そのまま意識を失うと。上から見ると、飛び込んだのにいつまで経っても浮いてこないという状況になりますよね。そういう形で多くの場合が命を失うということになります。
ポイントは、どうして今回飛び込みに失敗したのかがわからない。失敗したら、もう死んじゃうので。成功時と失敗時の差が、肺の中に空気を溜めていたか否かだという点が分かっているといいのですが、本当にたった1回の失敗で命を失ってしまうということになりかねない。いずれにせよ、やはり高い所から飛び込むのはやめた方がいいと思いますね」
「人工構造物の近くでは遊ばない」「深い所に限って水の流れが弱い。だから近づいてしまう。安全と思って近づいて入ったら、思わぬ深さに溺れてしまう」

Q 水難事故を防ぐために、我々市民ができることや、持つべき心構えをまとめていただけますか?
「まず1つは、やはり人工構造物の近くでは遊ばない。
2つ目に、もし川に入るなら、深さを確認して入っていく。その際に、ひざ下までの水深の場所で遊ぶに留める。それ以上深い所には行かないというふうにするといいと思います。
3つ目なんですけれども、子ども連れの方などは、ぜひとも一家揃ってライフジャケットを着て遊んでほしいと思います。でもライフジャケットを着ても着なくても、『ひざ下までの水深』はぜひとも守っていただきたい。『川泳ぎ』とは言いませんよね。あくまで『川遊び』で留めるということに徹していただきたいと思います」
Q 水の流れの速さより “思った以上に深い”という点に一番のリスクがある?
「その通りです。流れの速さは見れば分かるじゃないですか。ものすごい流れになっていたら、誰も近づかないんですよ。ところが、深さは見てもわからない。だから近づいてしまう。
しかも深い所に限って水の流れが弱いんですよね。水の流れが弱くて、ここは安全だなと思って近づいてしまい、そのままひょいと入ったら、思わぬ深さに溺れてしまうということなので。目で見て、ここは安全そうだという所に実は危険が潜んでいて、その危険にはまってしまうと命を落としかねないということですよね」
川辺のバーベキューでは「到着してすぐ」が “魔の時間”

Q 野外のレジャーで、予定はしていなかったけど川や水辺があって、ちょっと入ってみようという形で遊んで、そこで事故に遭うというケースも多いと思います。事前に水に入るか入らないかを決めておくというのも重要でしょうか?
「もっと言うと、川の近くでキャンプやバーベキューをする場合は、間違いなく水に入ると思った方がいいですね。本当に暑い日が続いていて、目の前の冷たそうな水を見ると、誰でも入りたくなってしまうので。もう最初から川に入るもんなんだと思って、注意していくと。
一番怖いのが、親子でバーベキューに行って、お父さんお母さんがバーベキューの準備をしている間に、子どもが自分たちだけで『ちょっと川に遊びに行っていい?』って言ってしまうんですよ。それに『いいよ』と言ってしまうんですよね。お子さんが自分たちの手から離れて川に向かって、次に気づいた時には『あれ?うちの子がいない』となる。
バーベキューなどに行って、川の事故はいつ起こるかというと、意外と『到着してすぐ』というケースが多いんですよ」
流されたら… あお向けの状態で浮いて待つ!呼吸確保に全力を

Q もし、水に流されたり溺れそうになったりした場合はどうすればいいでしょうか?
「とにかく浮いて、呼吸を確保するということですね。例えば『背浮き』という方法があります。背浮きというのは、背中を下にして、あお向けの状態で水の上に寝るような感じになります。背浮きだと、口と鼻が空気中に出るので、呼吸を確保できるんですね。こうしてとにかく呼吸をすることに全力を尽くす。これが救助を待つ人の努力になってきます」
Q 陸にいる人に求められる行動は何でしょうか?
「まずはすぐに119番をかけて、消防の救助隊を呼ぶということです。これがまず基本なんです。それから次に、流されている人がもし浮いていたら、さらに浮き具になるような物を投げて渡す、例えば空のペットボトルです。そういった物を投げて渡すようにしてあげる。渡らなくても、ペットボトルをどんどん投げていく。そういうふうにして流されている人を常に見ながら、119番もかけて、今この辺りを流れているという情報を、どんどん知らせてほしいと思います」
「一般の人が飛び込んで救助するのは絶対に無理。救助法を習わずにいきなり飛び込めば、一緒に死ぬことになる」

Q 今年7月には徳島県上勝町で、川の深みにはまった人を救助しようとして飛び込んだ人が死亡するという、もう本当に痛ましい事故が起きました。“一般の人が水難救助を行うのは基本的には無理”と考えた方がいいのでしょうか?
「はい、絶対に無理です。それでも助けに行きたいという方がおられるならば、ぜひとも日本赤十字社の水上安全法救助員養成講習会がありますので、それを受講してしっかりとした訓練を受けて、救助技術をしっかり身に付けてください。
どんなに水泳ができる人でも、救助法を習わずにいきなり飛び込めば、みんな沈みます。特殊な訓練を受けていない人が、水中に飛び込んで救助するということは、一緒に死ぬということになりますので、絶対に無理だと頭の中に叩き込んでいただければと思います」